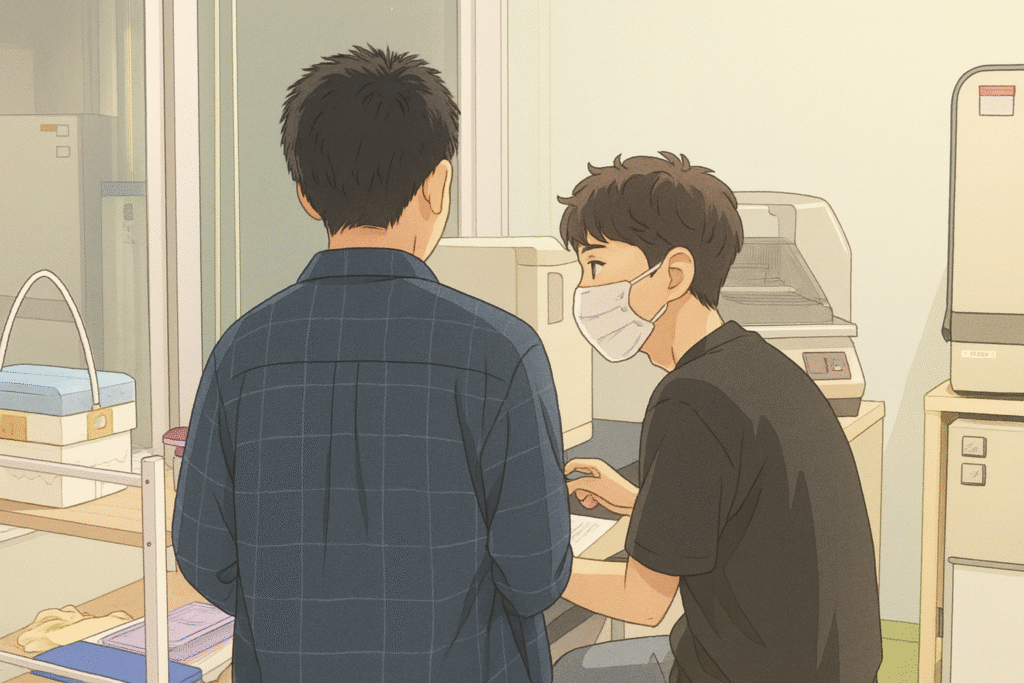秋の夜、金木犀の香りが路地の角にふんわりとたまっているように感じます。冷気を含んだ空気は澄み、屋根の上を渡る風が、昼間のざわめきをそっと洗い流していきます。ふと見上げると、星の粒が静かにまたたき、その中に小さな青い灯があるような気がして「よだかの星」を思います。
物語のよだかは、猛禽の鷹と名が似ているというだけでからかわれ、ついには鷹から改名を迫られます。助けを求めて他の鳥に近づいても冷たく退けられ、生きるために虫を食べるたび「ごめんよ」と心の中で詫びるほど、やさしさと痛みを抱えた鳥でした。逃げ場をなくしたよだかは、地上を去ろうと決め、宵の明星や赤く光る星々、天の川の向こうの群れ星にまで「迎えてください」と願いますが、答えはどれも冷ややかでした。それでもよだかは羽が焼けるような思いで高く高く飛びつづけ、やがて自ら青く光り、小さな星になります。名を手放さずに苦しみを抱えたまま高く飛んだ一羽の姿は、弱さを抱えた心にも寄り添ってくれるように思えます。連休明けですが、本日も学生たちが実験と解析を頑張ってくれました。私たちもまた、日々のつかれや迷いを胸にしながら、少しずつ澄んだ空へ顔を上げて、小さな光を見つけていきたいです。