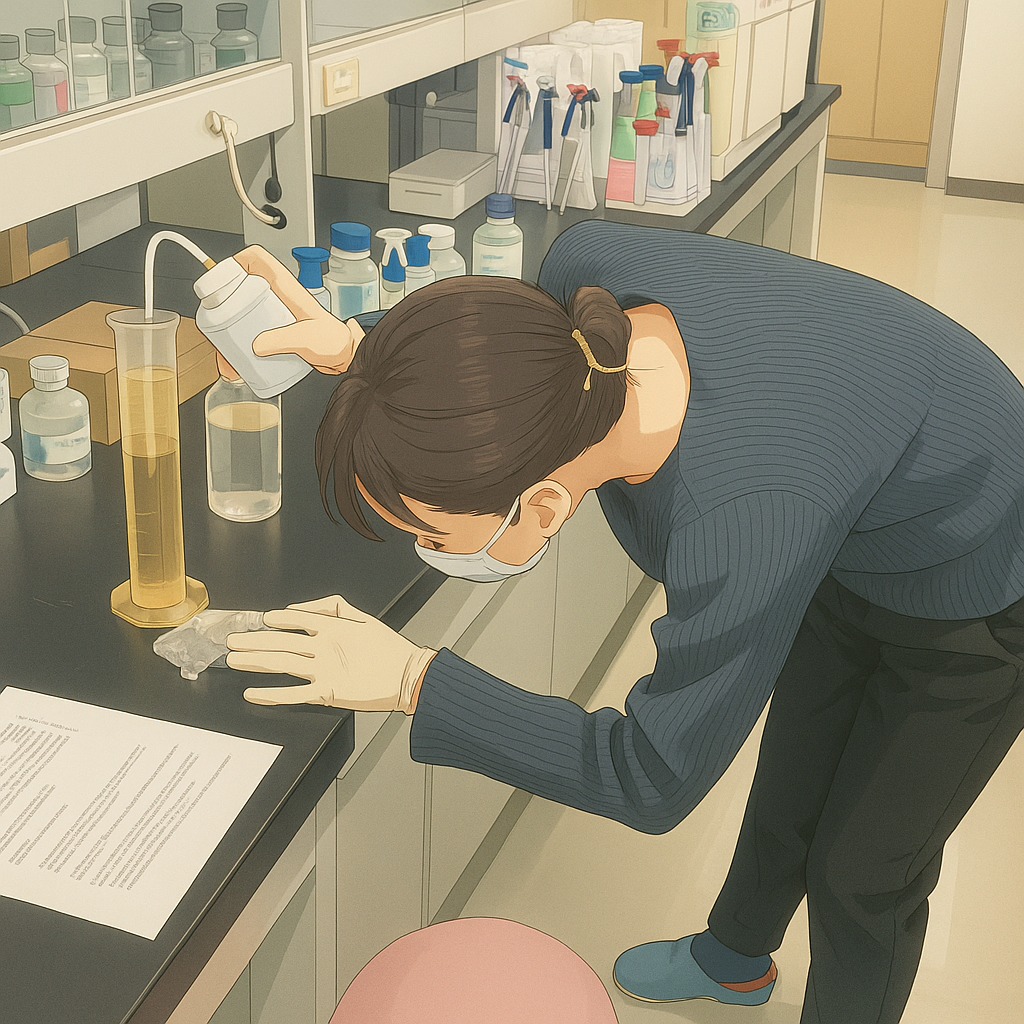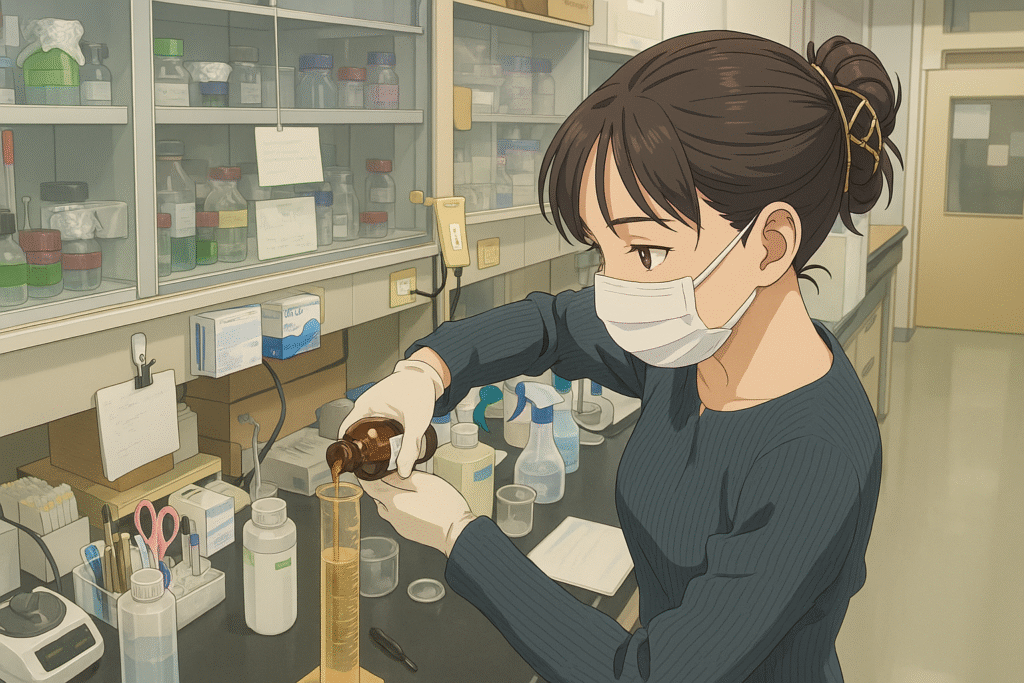1847年11月、エディンバラの産科医ジェームズ・ヤング・シンプソンは、同僚のキースとダンカンと自宅でクロロホルムを吸入し、人で強い麻酔作用を実証しました(実験日は4日夜説が有力ですが資料間に揺れがあります)。11月8日に分娩で初使用、10日に学会で報告し、小冊子で直ちに公開しました。エーテルより少量(数十滴)で導入が速く、刺激臭が弱く非可燃で、安価かつ携帯容易、ハンカチやスポンジでも投与できる扱いやすさが評価され、産科・外科に急速に普及しました。1853年のヴィクトリア女王の分娩での使用は社会的受容を決定づけました。当時の宗教倫理論争にも影響を与えました。一方、1848年の急死例で安全域の狭さや心毒性が問題化し、ジョン・スノウが濃度調節可能な吸入器を設計しました。その後は地域差のあるエーテル派との併存を経て、20世紀にはより安全な揮発性麻酔薬へ置換が進みました。化学的には1830年代に合成と命名が確立しており、エディンバラのダンカン&フロックハート社が供給を担いました。初期には歯科でも抜歯に用いられ、臨床領域が広がりました。こうした過程を通じ、麻酔は薬剤だけでなく、用量・器具・監視を統合する臨床管理学へと発展しました。
本日も、学生たちが実験と解析を頑張ってくれました。学会が近い学生はデータの整理と解析に余念がありません。M4の学生の方は、長時間の顕微鏡撮影を頑張ってくれました。大学院生はディスカッションと行動解析を行いました。どうにも集中力が続かないことが悩みですが、若い力に負けずに論文執筆を頑張ります。
Losing is not an option.