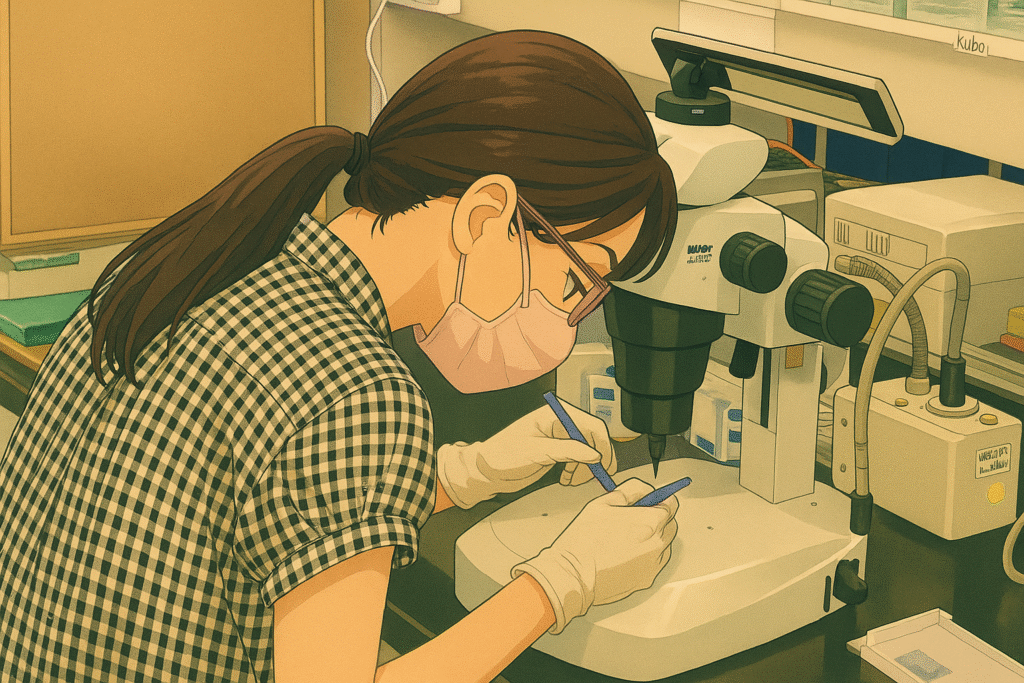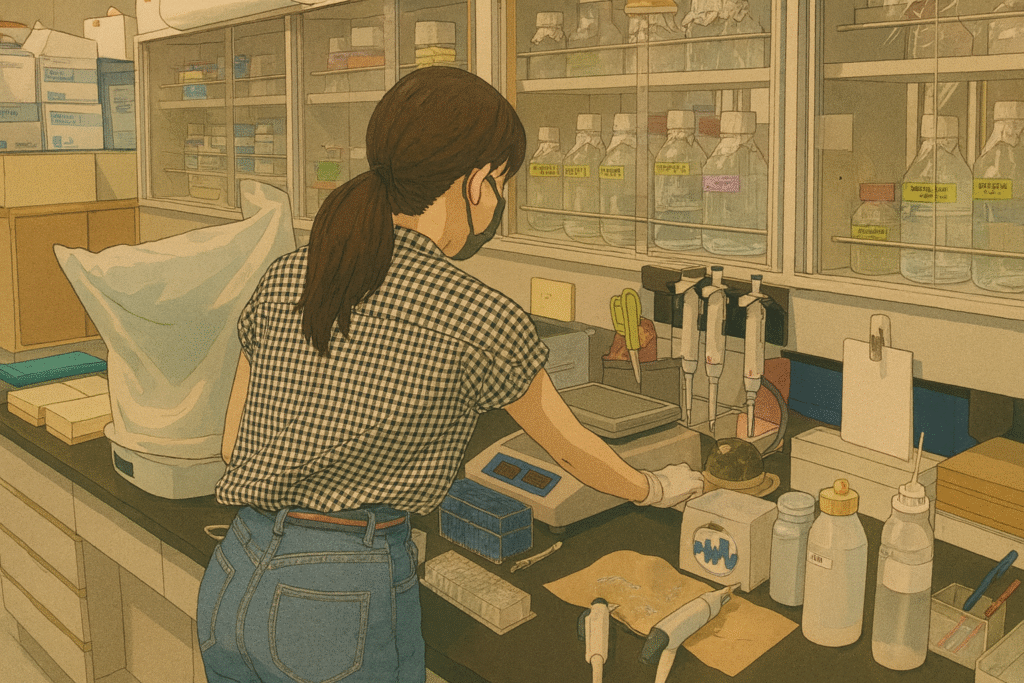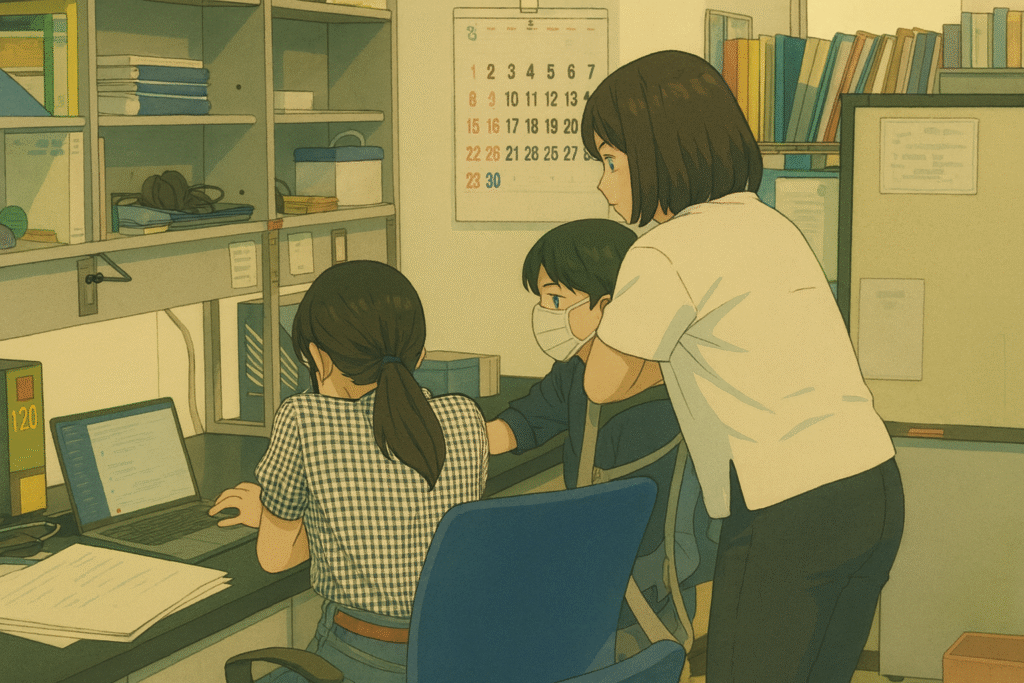本日は朝から雲が多い天気となりました。午後から医学類の学生が来室して、実験とデータの解析を行ってくれました。中間発表会を終えた医療科学類の学生2名も実験と検鏡を行いました。大学院生は、インターン(オンライン)とディスカッションと実験とデータ解析を頑張りました。M1の早期から、就職活動するのは大変そうです。努力が実を結ぶことを祈っています。
1928年9月3日、イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングは、ロンドンのセント・メアリーズ病院で黄色ブドウ球菌を培養している最中に、偶然混入したカビの周囲で細菌が溶けている現象を観察し、このカビが分泌する物質を「ペニシリン」と命名しました。当時、感染症は主要な死因であり、梅毒に対するサルバルサンなど限られた化学療法剤しか存在しなかったため、細菌全般に有効な薬の登場は切望されていました。しかしフレミング自身には不安定なペニシリンを純粋に抽出・大量生産する技術がなく、彼の発見はしばらく研究室内の知見にとどまりました。その後、1930年代末からオックスフォード大学のフローリーやチェイン、ヒートリーらが抽出・精製法を確立し、さらに第二次世界大戦中にはアメリカの製薬会社やUSDAが深槽発酵や高生産株(メロン🍈に由来します)の利用によって工業的な大量生産を実現しました。これにより戦場での感染症治療に劇的な効果を発揮し、「奇跡の薬」と呼ばれるようになったペニシリンは、肺炎や敗血症、梅毒など多くの致死的疾患を治療可能にし、平均寿命の延伸に大きく貢献しました。その成果は1945年にフレミング、フローリー、チェインがノーベル生理学・医学賞を受賞することで評価され、ペニシリンの発見と実用化は、抗生物質の時代を切り開いた20世紀最大の医学的革命のひとつとして位置づけられています。
普段の研究は地味な作業がほとんどです。他人が出したデータをたくさん集め、上手にパッケージングしてきれいに提示するのが流行りですが、解剖学の原点に立ち返り、生データを自分で積み重ねて、「自然の女神」の素顔に迫る研究を行いたいものです。