本日の日中は、学会期間中とは打って変わり暖かいというより暑く感じるほどでした。日が落ちてからは風が強く、冷たい春に戻ってしまいました。M4の学生の方がin vitro実験を行ってくれました。生き物を相手にする実験は、どうしても実験対象に寄り添う必要が出ます。M4は春休みなしで実習がありますが、学会にも実験にもコンスタントに取り組んでくださり、とても頼もしいです。研究棟の周囲では、ハクモクレンの花が咲いており、風にのってその香りが漂っています。
東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ
この和歌は、平安時代の学者・政治家であった菅原道真が、太宰府(現在の福岡県)に左遷される際に詠んだとされています。道真は自宅の庭に梅を大切に植えており、その梅の花との別れを惜しんだ心情が表れています。「春の東風が吹いたら、私の大切な梅の花よ、香りをこの太宰府まで届けてくれ。主人(私)がいないからといって、春が来たことを忘れないで咲いておくれ」という意味です。
春は出会いと別れの季節とされ、多くの人が新たな旅立ちや別れを経験します。菅原道真が詠んだ「東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」は、まさにそのような春の別れの情景を象徴する和歌です。道真は、都を離れ太宰府へと左遷される無念さと、愛する梅の木との別れを惜しむ気持ちを詠みました。梅の花に「春を忘れないで咲いてほしい」と願う姿は、別れの中にあっても変わらぬ季節の巡りと希望を重ねているようです。春は、別れの寂しさを伴いながらも、新しい始まりの兆しを感じさせる時期です。この和歌は、春に訪れる別れの切なさと、それでも変わらず春が訪れることへの静かな願いを私たちに伝えています。春の別れは悲しみだけでなく、未来への期待も秘めていることを改めて教えてくれる作品です。
この和歌に重なるのが「一陽来復」という言葉です。冬が終わり、再び太陽の光が戻るように、どんな苦難の後にも必ず良い時期が訪れるという意味です。春はまさに「一陽来復」の季節であり、別れや悲しみを経験した人々に新たな希望を運んでくれます。道真のように、困難の中でも春の訪れを信じる心は、未来への力強い一歩となります。私たちも春の風に花の香りを感じるたびに、「一陽来復」を思い出し、別れの先に待つ新たな出会いや可能性に期待を膨らませて歩みたいものです。


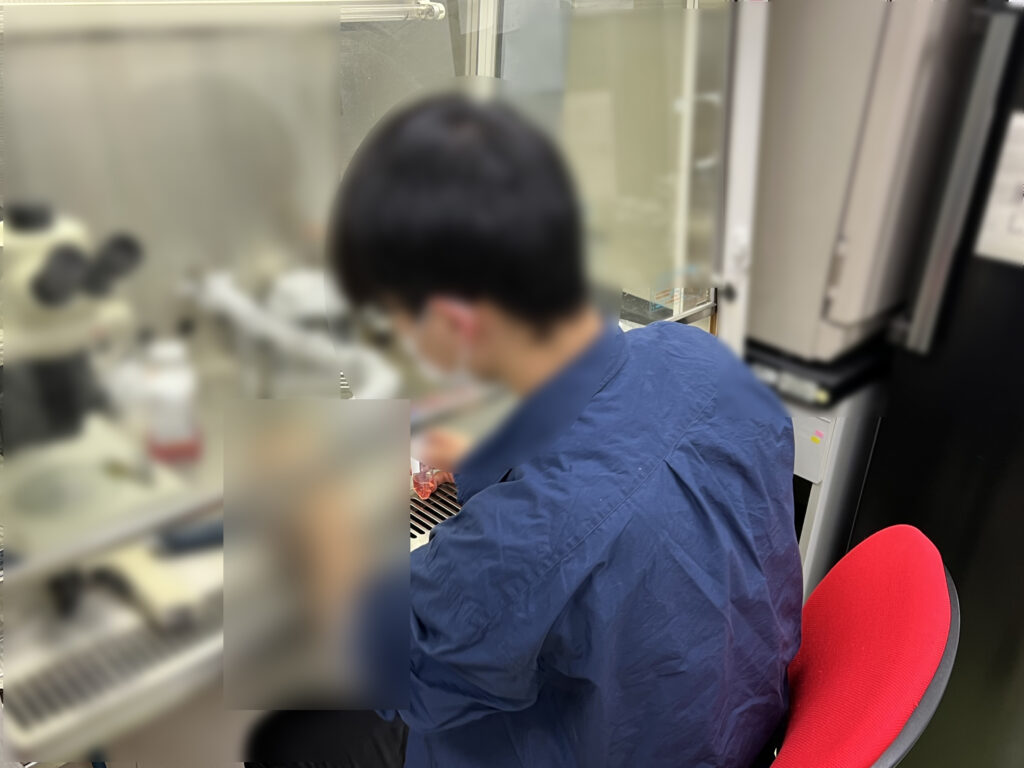
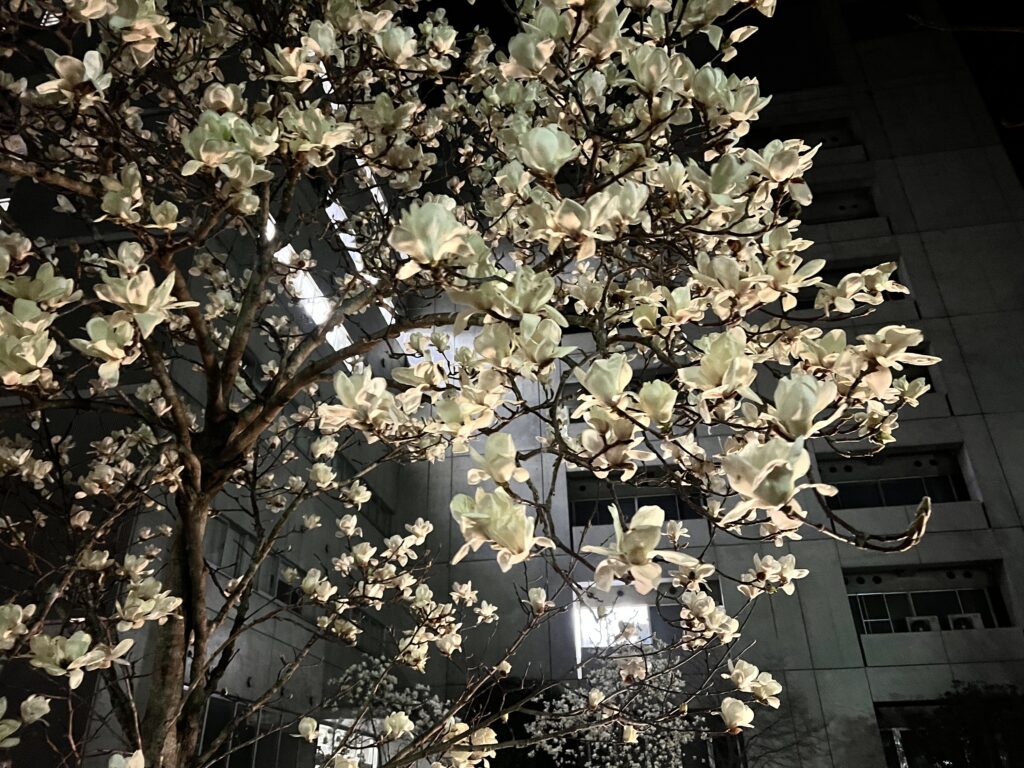


“東風吹かば-Si le vent vient de l’est” への1件のフィードバック