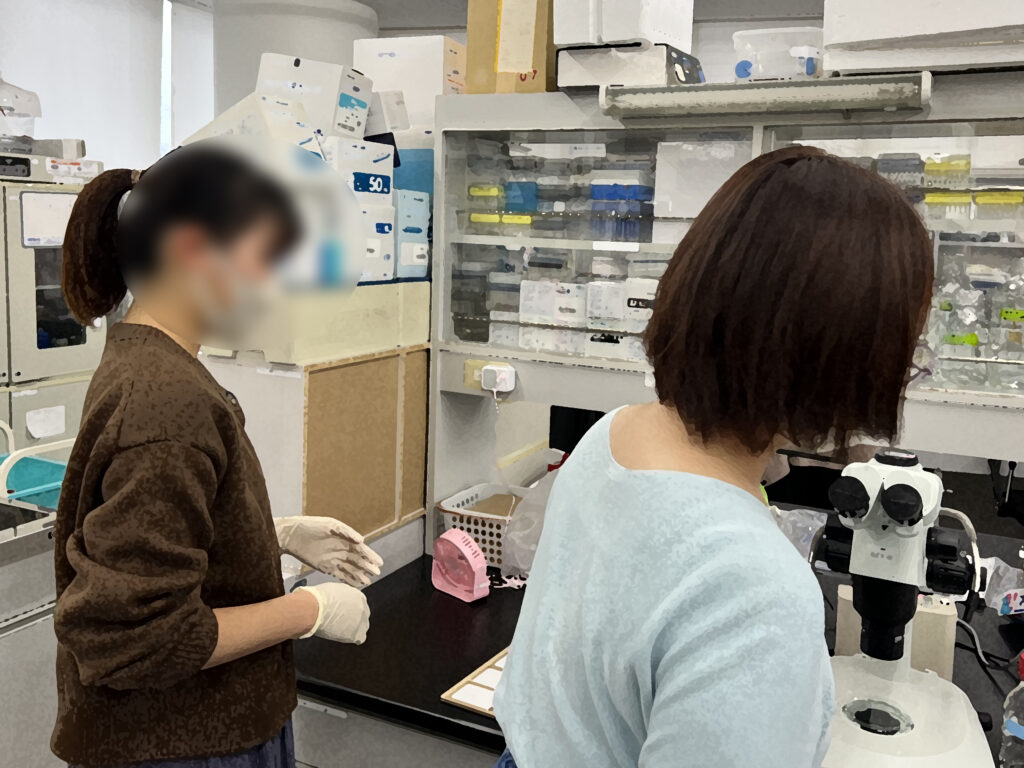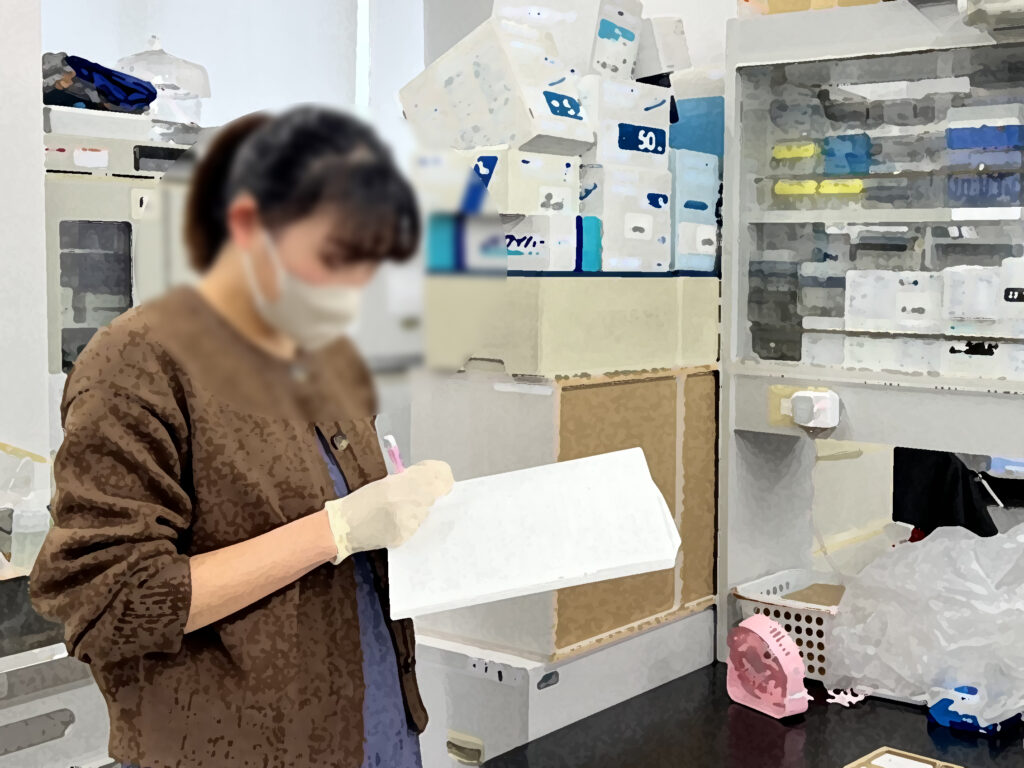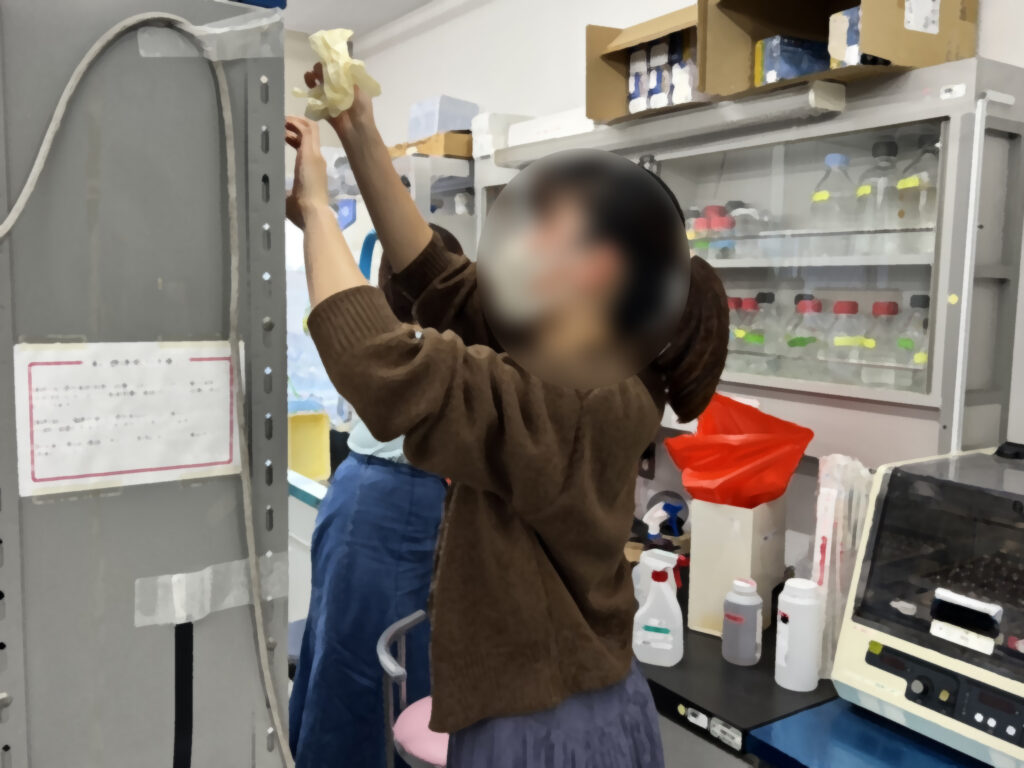早朝は濃霧が大学一帯を覆っていました。年に何回か濃霧が発生し、豊潤な水気と幻想的な景色を見ることができます。昼に研究棟から出ると、モクレンの花が開花していました。いよいよ春に季節が推移しているようです。本日は、医療科学類国際医療科学主専攻の留学生が実験を行いました。研究支援員と学会を控えた学生たちが実験と学会発表の準備、データの解析を頑張ってくださいました。彼らの頑張りに応えるべく、早朝から事務処理を頑張りましたが、怒涛のメール攻勢で夜になってしまいました😢
霧は空気中の水蒸気が微細な水滴として凝結し浮遊する現象で、発生には湿度上昇、凝結核の存在、空気の冷却が必要です。主な発生原因には、夜間の地表放射冷却による放射霧、暖かく湿った空気が冷たい表面上を移動する移流霧、前線付近で発生する前線霧、冷たい空気が暖かい水面上を通過する蒸気霧、湿った空気が山を上昇する山岳霧、大気汚染物質が凝結核となる都市霧があります。発生を促進する要素として、盆地や谷間などの地形条件、弱風や高湿度といった気象条件、温度差が大きい季節的要因が挙げられます。
つくば市一帯は霧の発生が比較的多い地域です。この原因として、筑波山(標高877m)と関東平野東端部という地形的特徴、霞ヶ浦や小貝川などの水源による水蒸気供給が挙げられます。つくば市の霧は季節ごとに特徴があり、春季(3-5月)は暖かい日中と冷え込む夜間の温度差により早朝に放射霧が発生しやすく、4月頃は月に5〜7日程度の霧日数があります。夏季(6-8月)は比較的発生が少なく、秋季(9-11月)は10月下旬から11月にかけて放射冷却と地表湿度の組み合わせにより増加し、月に8〜10日程度になります。冬季(12-2月)は冬の冷え込みによる放射霧が頻発し、特に早朝に濃い霧が見られます。
つくば市には気象研究所があり、詳細な観測記録が蓄積されています。年間平均での霧日数は約40〜50日(視程1km未満)で、視程100m未満の濃霧は年間10日前後です。また農業環境技術研究所の観測から、霧発生の時間的・空間的パターンには市内でも地域差があることが判明しています。
霧は視程を低下させるため交通への影響が大きく、特に常磐自動車道やつくばエクスプレス沿線、筑波山周辺の山道では危険性があります。一方で、気象研究所やJAXAなどの研究機関による霧の研究、リモートセンシング技術を活用した観測・予測システムの開発にも貢献しています。
つくば市の霧は、独特の地理的条件と気象条件の組み合わせにより、関東地方の中でも特徴的な発生パターンを示しており、季節による変動はあるものの、年間を通じて霧の発生が観測される地域といえるようです。
物理的にも精神的にも濃い霧の中を彷徨う状態が続いていますが、過去を振り返ることなく、春の陽光の如き才能と前のみを見て歩きたいものです。