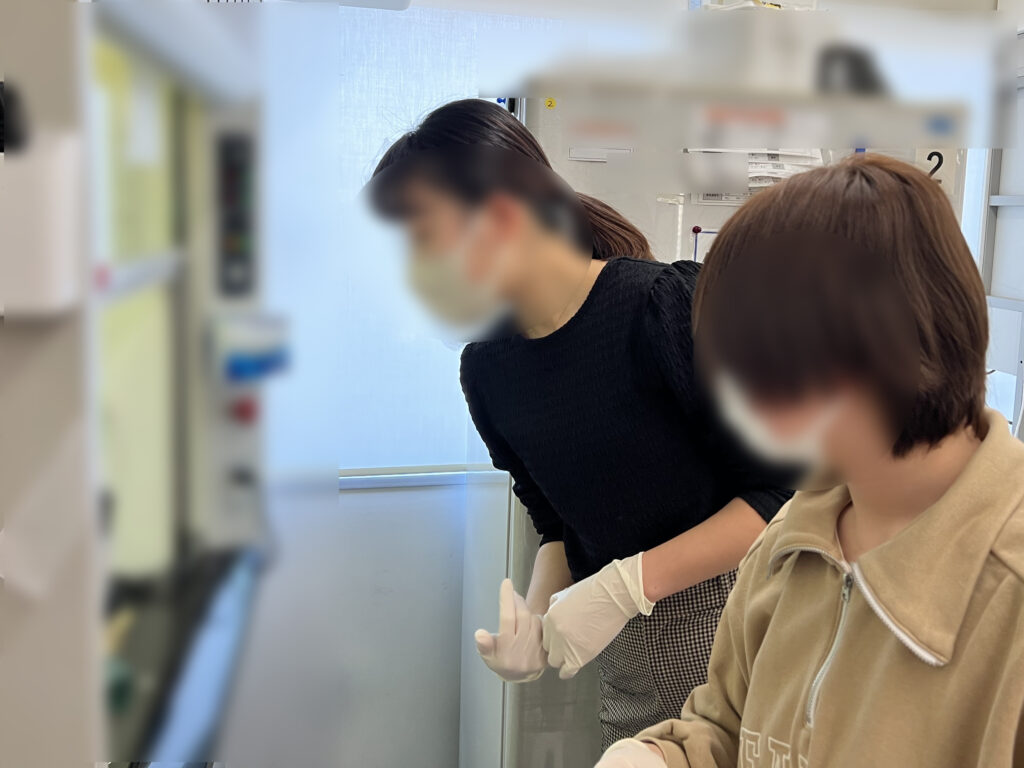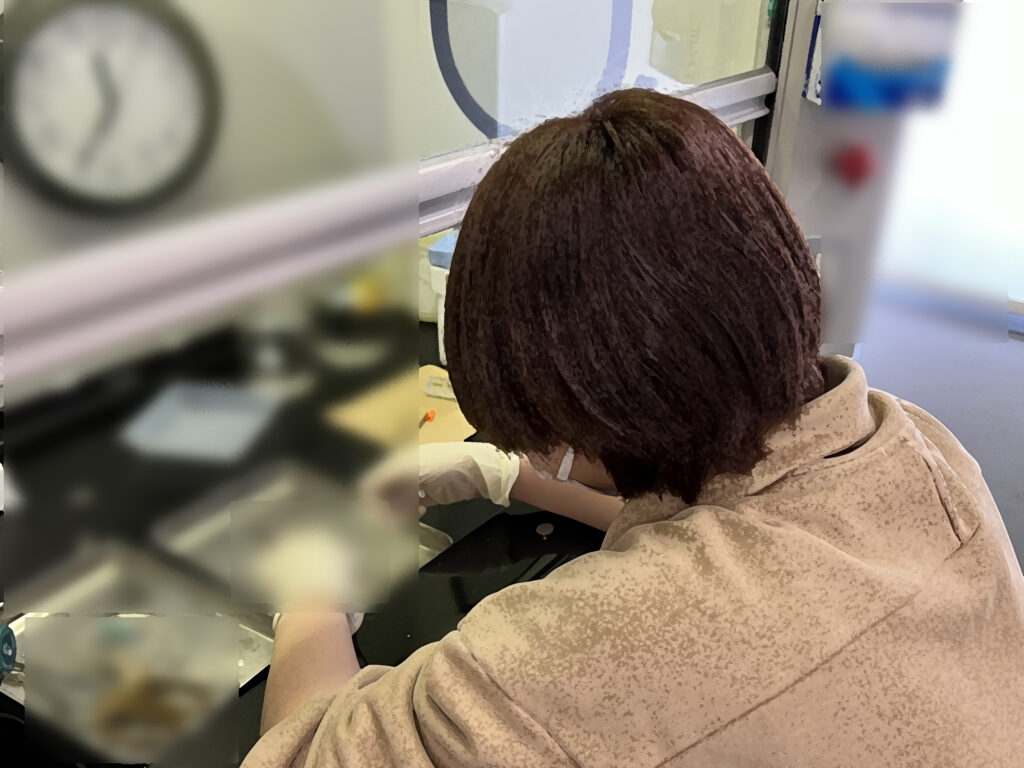本日もM3の学生の方が学会の準備をしてくださいました。これまで依頼した作業のように、迅速にポスターを作成しています(智謀湧くが如しです。自分ならできそうにないです💦)。生物学類の学生と研究支援員の方が、実験を行ってくれました。夜になって、臨床実習を終えたM4の学生の方も研究室に来て、学会発表の準備や実験の準備を行いました。お疲れのところ、いつもありがとうございます!
研究室では、スタッフは学群・大学院の講義や実習、学外、学内の仕事があり、いつも研究室にいるとは限りません。学生は、講義や実習、就職活動、アルバイトなどを掛け持ちしており、いつも同じ学生が研究室にいるとは限りません。研究は、ひとりではできない(ことが多い)のでコミュニケーションの取り方を考える必要があります。
同期的コミュニケーションと非同期的コミュニケーションは、情報をやり取りする際のタイミングの違いによって区別されます。用途や状況に応じて、これらのコミュニケーション手法を使い分ける必要があります。研究室では、データベースやスプレッドシート、Skackなどの非同期的コミュニケーション(運用がなかなか難しいケースが多いように感じます)を最大限に活用しつつ、同期的コミュニケーションも意識して実施する(必要に応じてミーティングする、教員から話しかける、など)ようにしたいものです。
同期的コミュニケーション
同期的コミュニケーション(Synchronous Communication)は、リアルタイムで情報をやり取りする形式のコミュニケーションです。この方法では、参加者全員が同時にコミュニケーションに参加しており、すぐに応答を返すことが期待されます。代表的な例として、以下が挙げられます:
- 対面会議や打ち合わせ:その場で直接話し合いが行われ、即座に意見交換が可能です。
- 電話やビデオ通話:相手がその場で応答し、リアルタイムでのやり取りが行われます。
- チャット:特に即時の応答が期待される場合には同期的な要素を含みます。
同期的コミュニケーションの利点としては、問題や疑問がその場で解決されやすいこと、意見や感情のニュアンスが直接伝わりやすいことが挙げられます。しかし、参加者のスケジュール調整が必要になるため、実施するためのコストや負担が大きくなることがあります。コロナ禍以降、講義が録画されて何度も見直しができることなどから、口頭で伝えたことに対する(一過性の情報に対する)執着心が弱くなっているようにも感じます。
非同期的コミュニケーション
非同期的コミュニケーション(Asynchronous Communication)は、リアルタイムに応答が求められない形式のコミュニケーションです。参加者は自分の都合に合わせてメッセージを受け取り、応答を返すことができます。代表的な例として、以下が挙げられます:
- 電子メール:送信後、相手が都合の良いタイミングで確認し、応答します。
- メッセージングアプリ(例:SlackやMicrosoft Teams):リアルタイムでの応答も可能ですが、通常、非同期的な使用が期待されます。
- タスク管理ツールやプロジェクト管理ソフト(例:TrelloやAsana):メンバーが進捗を報告し、必要に応じて後から確認することができます。
非同期的コミュニケーションの利点としては、各参加者が自分のペースで対応できるため、時間的な制約が少ないことや、情報の確認や応答に十分な時間をかけることができることが挙げられます。しかし、リアルタイム性がないため、問題解決までに時間がかかる場合や、誤解が生じるリスクもあります。学生に、このシステムが研究室にあることやスプレッドシートが共有されていることを伝えるのですが、十分に理解されていないことが多いように感じます。
それぞれのメリットとデメリット
同期的コミュニケーションと非同期的コミュニケーションには、それぞれメリットとデメリットがあり、場面や目的に応じて適切な方法を選択することが重要です。
A-1. 同期的コミュニケーションのメリット
- リアルタイムでの即応性:
- 問題や疑問がその場で解決されやすく、意思決定が迅速に行えます。特に緊急時や早急なフィードバックが必要な場合に適しています。
- 感情の伝達がしやすい:
- 対面やビデオ通話では、表情や声のトーン、ジェスチャーなどが直接伝わるため、意図や感情を誤解されにくく、信頼関係の構築にも役立ちます。
- アイディアの共有やブレインストーミングに効果的:
- 参加者全員がその場で意見を交換しやすいため、アイディアを迅速に引き出すことができ、創造的なディスカッションが活発化しやすくなります。
- 双方向性が高い:
- 互いにリアルタイムで応答することで、コミュニケーションが双方向に進むため、質問や追加情報の提供が容易です。
A-2.同期的コミュニケーションのデメリット
- スケジュール調整が必要:
- 参加者全員が同じ時間に揃う必要があり、特に複数の時間帯にまたがるチームでは調整が難しいことがあります。
- 時間的・場所的な制約:
- 場所に集まることが求められたり、特定の時間に縛られたりするため、柔軟性が少なく、他の作業を中断しなければならない場合があります。
- 集中力や労力が必要:
- リアルタイムの応答が求められるため、参加者は集中して応じる必要があり、精神的な負担がかかりやすいです。
- 中断のリスク:
- 特にチャットや電話で頻繁に同期的コミュニケーションが行われると、他の作業が中断され、生産性が低下する可能性があります。
B-1. 非同期的コミュニケーションのメリット
- 時間的な柔軟性:
- 各参加者が自分の都合の良いタイミングで応答できるため、異なるタイムゾーンのチームメンバー間でもスムーズにやり取りができます。
- 深く考えた応答が可能:
- メッセージを受け取った後に考える時間があるため、内容を熟考した上で応答ができ、質の高いフィードバックや意見が期待できます。
- 中断が少ない:
- 非同期的なやり取りのため、他の作業を中断せずに済み、個々の業務に集中しやすくなります。生産性の維持に役立ちます。
- 記録が残る:
- メールやメッセージアプリを利用する場合、すべてのやり取りが記録されるため、後で確認しやすく、情報の管理にも便利です。
B-2. 非同期的コミュニケーションのデメリット
- 応答に時間がかかる:
- 即時の返答が得られないため、問題解決に時間がかかることがあります。緊急性が高い場合や、すぐに対処が必要な場合には不向きです。
- 感情や意図が伝わりにくい:
- テキストだけでのやり取りでは、意図や感情が伝わりにくく、誤解やミスコミュニケーションが生じやすいです。必要に応じて、補足の説明や表現に気を遣う必要があります。
- 返信を待つストレス:
- 他の人の応答を待つ時間が生じるため、タスクやプロジェクトが中断されることもあり、進行の遅延につながる可能性があります。
- プロジェクトの一体感が損なわれる:
- リアルタイムのやり取りが少ないため、チームとしての一体感や結束力が薄れ、孤立した感覚が生じやすくなることがあります。
まとめ
- 同期的コミュニケーションはリアルタイムでの応答が必要で、直接的なやり取りが可能ですが、時間的な制約が大きいです。
- 非同期的コミュニケーションは即時の応答を求めず、自由なタイミングでのやり取りが可能ですが、リアルタイム性に欠ける場合があります。
研究室では、人それぞれpriorityが異なり、研究に一意専心というわけにはいかないのが難しいところです。研究を強力に推進してくださる方を求めています。興味がある方はスタッフまで是非お声がけください。