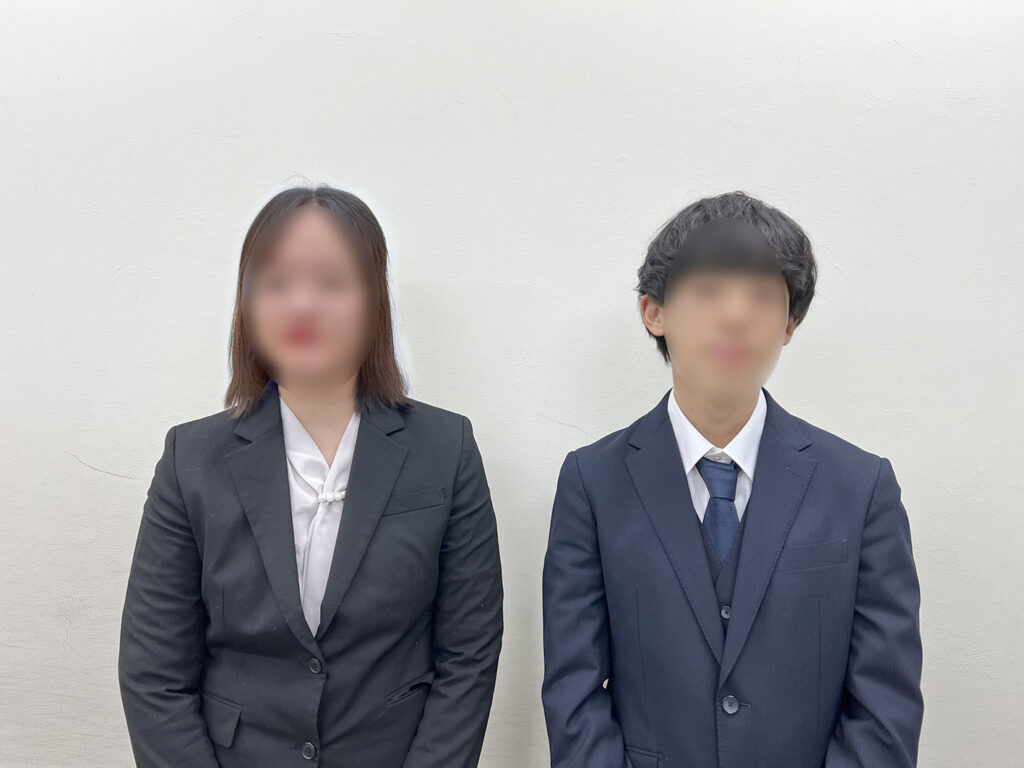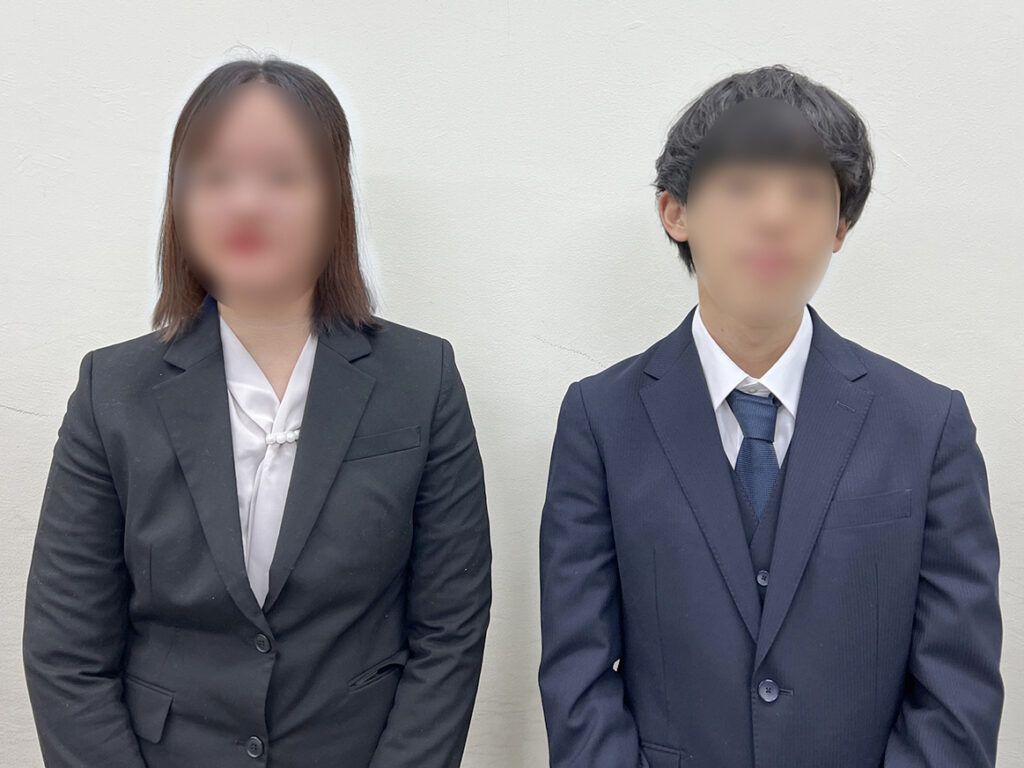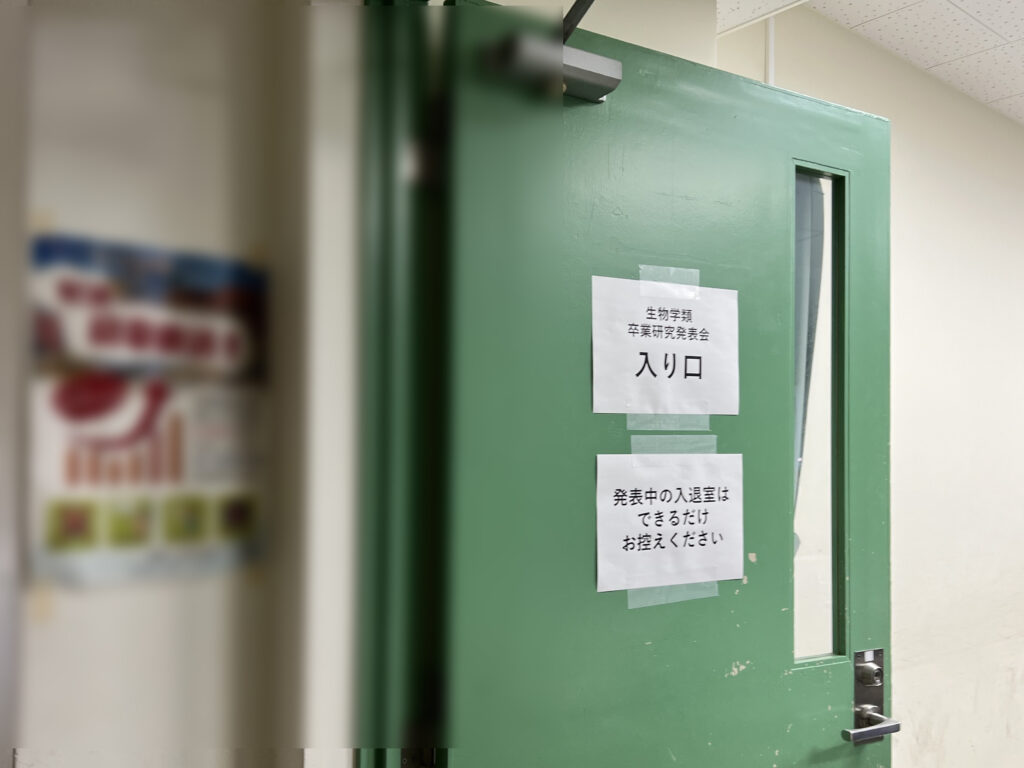生命環境学群生物学類卒業研究発表会が開催されました。多彩な生物を対象とした、興味深い研究成果を聴くことができました。当研究室からはHさんとKさんが発表しました。卒業研究の内容をしっかりと話してくれました。大変お疲れ様でした。春からは、大学院生として研究室を引っ張ってくれることでしょう。
生物学類の卒業研究発表会では、計74件の研究発表が行われました。発表は生態学、分子生物学、行動学、遺伝学、微生物学、神経科学など、多岐にわたる分野をカバーし、4会場に分かれて行われました。それぞれの会場では、進化生物学、発生学、脳科学、計算生物学、植物科学などのテーマごとに発表が行われ、活発な議論が交わされました。本発表会は、学生たちが卒業研究の成果を発表し、学術的な交流を深める貴重な機会となりました。
1. 生態学・行動学
生態学・行動学の分野では、花粉媒介者であるハチの行動や植物の適応戦略に関する研究が多く発表されました。例えば、マルハナバチの花選びにおける学習効果や、ハダニの雄が繁殖戦術と捕食回避行動をどのようにバランスさせるかについての研究が発表されました。また、都市部におけるハチ類の多様性を評価するための**「Bee hotel」を用いた管住性ハチ類の営巣環境調査**では、土地利用の違いがハチの多様性にどのような影響を与えるかが明らかになりました。
2. 遺伝学・発生学
遺伝学・発生学の分野では、寄生蜂の毒がショウジョウバエ幼虫の成虫原基に及ぼす影響の解析や、ウニ幼生におけるWnt7遺伝子の機能解析が行われました。また、発生メカニズムに関する研究として、伊豆半島沖の水深50m以深での貝類相調査や、ヒドロ虫に寄生する未記載種の扁形動物の分類学的解析などが発表されました。
3. 分子生物学・生理学
植物や動物のストレス応答機構に焦点を当てた研究が多く見られました。例えば、ポプラの塩ストレス応答に影響を与えるRNAシャペロンの解析や、シロイヌナズナのガラクチノール合成酵素の異所的発現が気孔調節に及ぼす影響についての研究が報告されました。
4. 神経科学関連の研究
神経系の研究も多数発表され、精神疾患、睡眠、生理機能、神経細胞の分子メカニズムに関する発表が目立ちました。主な研究テーマは以下のとおりです。
- 統合失調症関連キネシンKIF17がミクログリア形態変化に果たす役割の解明
- 自閉症関連タンパク質Hevin/Sparcl1変異体の機能解析
- ミクログリアにおける膜貫通型タンパク質TREM2の新規機能の解明
- IL-17RA/RCの大脳皮質における時空間発現と精神疾患モデルにおける神経免疫連関の検討
- ヒストンメチル化が睡眠要求の分子メカニズムに与える影響
- REM睡眠剥奪が恐怖記憶形成および文脈弁別に果たす役割
- SIK3-シャペロン結合が睡眠覚醒制御に及ぼす影響
特に、統合失調症や自閉症スペクトラム障害(ASD)に関連する分子機構の研究が進められ、ミクログリアや神経免疫連関の影響を調査する研究が注目されました。また、睡眠と記憶の関連を分子レベルで解析する研究も行われ、ヒストン修飾や特定のキナーゼの役割について新たな知見が示されました。
5. 微生物学・腸内細菌研究
腸内細菌と宿主の相互作用に関する研究も活発に行われました。例えば、オカダンゴムシの腸内細菌が産生する抗カビ物質の特性や、腸内細菌 Ruminococcus gnavus の宿主の食餌依存的な定着メカニズムが解析されました。また、セサミン代謝菌の分布解析も行われ、腸内微生物が宿主の健康に与える影響についての理解が深まりました。
6. 計算科学・バイオインフォマティクス
分子シミュレーションを用いた研究も発表されました。例えば、味覚受容体の認識メカニズムや、核輸送受容体HikeshiとHsc70の熱依存的な結合メカニズムの解析が計算科学的手法で解明されました。また、類似細胞検索のためのWebアプリケーション「Cell similarity search」の開発も報告され、実験データ解析の新たなツールとして注目されました。
総括
筑波大学生物学類の卒業研究発表会では、74件の研究発表が行われ、生態学、遺伝学、神経科学、微生物学、分子生物学、計算生物学など幅広い分野が取り上げられました。特に神経科学分野では、統合失調症や自閉症の分子メカニズム、睡眠と記憶の関係、ミクログリアの機能についての研究が数多く発表され、精神疾患や神経変性疾患の病態解明に向けた研究が進められました。また、環境要因と生物の適応に関する研究も多く、ポリネーター(花粉媒介者)や腸内細菌との相互作用、土地利用と生態系の関係など、応用的な視点を持つ研究が多数発表されました。本発表会は、筑波大学生物学類の学生たちがこれまでの研究の集大成を披露する場であり、学術的な議論を通じて新たな知見を深める貴重な機会となりました。発表者の皆さん、研究指導の先生方、運営に携わった皆様、お疲れ様でした。
- Asumi Kubo A, Momo Morikawa, Suguru Iwata, Tetsuya Sasaki, Yosuke Takei. Spatiotemporal analysis of IL-17RA/RC expression in the cerebral cortex: examination of neuroimmunological links using a model of psychiatric disorders. Graduation Thesis Presentation, College of Biology. 2025.02.18. Tsukuba.
- Mitsuhiro Hyugaji, Momo Morikawa, Tetsuya Sasaki, Suguru Iwata, Yosuke Takei. Elucidation of the role of the schizophrenia-related kinesin KIF17 in microglial morphological changes. Graduation Thesis Presentation, College of Biology. 2025.02.18. Tsukuba.
- Kubo A, Morikawa M, Iwata S, Sasaki T, Takei Y. Spatiotemporal analysis of IL-17RA/RC expression in the cerebral cortex: examination of neuroimmunological links using a model of psychiatric disorders. Tsukuba Journal of Biology. 2025-02. 24 (1). 50-50.
- Hyugaji, Morikawa M, Sasaki T, Iwata S, Takei Y. Elucidation of the role of the schizophrenia-related kinesin KIF17 in microglial morphological changes. Tsukuba Journal of Biology. 2025-09. 24 (1). 51-51.
卒業研究発表会に参加して (生物学類Hさん)
私は本発表会において、「統合失調症関連キネシンKIF17がミクログリア形態変化において果たす役割の解明」と題し、自身の卒業研究の成果を報告いたしました。
学類内向けのイベントではありましたが、これまで学会等での発表経験がなかったため、少し緊張や不安もありました。資料作成にあたっては、生物学類にはさまざまな専攻分野や異なる関心を持つ学生や先生方が在籍していることを念頭に置き、多くの方に理解しやすいものを心がけました。限られた発表時間の中で、発表内容の「正確さ」と「伝わりやすさ」のバランスを取ることは難しく感じましたが、資料を作成する過程で、自身の研究の到達度やこれまで気づけていなかった課題を明確にすることができました。
当日は多くの方に発表を聞いていただき、質疑応答ではさまざまなフィードバックをいただくことができました。また、学類同期の発表を聴講する中で、テーマ設定や実験のアプローチ、スライドのより良い見せ方など、多くの気づきを得ることができました。発表会で得た経験を、今後の研究活動に生かしていきたいと思います。
本研究を遂行するにあたり、お世話になった解剖学・神経科学研究室の皆様、発表会の開催に関わってくださった先生方、準備委員の皆様に、心より感謝申し上げます。