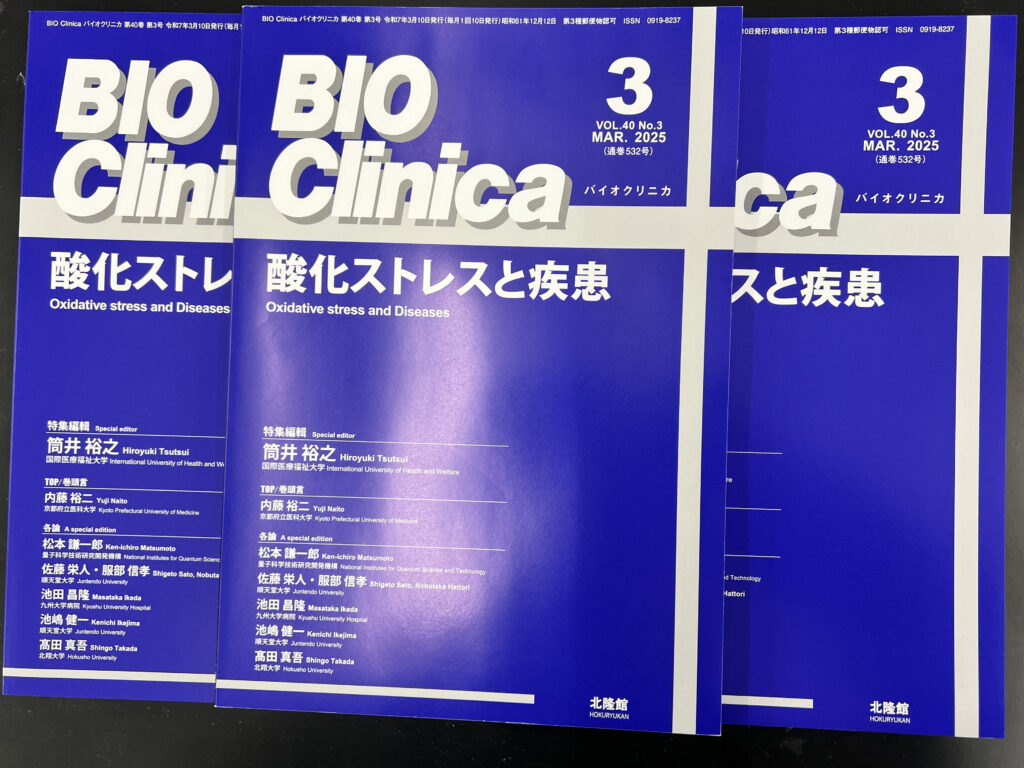2月は、冬の厳しさが続く一方で、春の兆しを感じさせる伝統行事や風習が多く見られる月です。日本の旧暦では立春が一年の始まりとされており、その前日の節分は、邪気を払い、新たな年を迎える重要な行事として親しまれています。節分の日には、炒った大豆をまいて「鬼は外、福は内」と唱えながら邪気を払う習慣があり、近年では恵方巻を恵方を向いて無言で食べることで願いが叶うとする風習も定着しています。節分の翌日にあたる立春には、「立春大吉」というお札を玄関に貼り、一年の無病息災を願う習わしがあり、また寒さの中で身を清めるために水行を行う人々の姿も見られます。
2月8日には、裁縫に関わる人々が古くなった針に感謝し、それを供養する「針供養」の行事が行われます。折れたり錆びたりした針を柔らかい豆腐やこんにゃくに刺し、その労をねぎらいながら、裁縫の技術向上を祈るこの風習は、ものを大切にする日本人の心を象徴するものといえるでしょう。また、かつて日本の一部では旧暦の正月を祝う習慣があり、特に沖縄などでは今でも旧正月に餅つきをしたり、おせち料理を楽しんだりする風習が残っています。
2月最初の午の日には、商売繁盛や五穀豊穣を祈願する「初午」の祭りが全国の稲荷神社で催されます。稲荷神の使いである狐が油揚げを好むとされることから、初午の日にはいなり寿司を食べる習慣が根付いています。また、2月19日頃には二十四節気の一つである「雨水」を迎え、雪が雨へと変わることで春の訪れを実感する時期とされています。この日には、雛人形を飾ると良縁に恵まれるという言い伝えもあり、ひな祭りの準備を始める目安ともなっています。
2月23日は今上天皇である徳仁天皇の誕生日にあたり、皇居では一般参賀が行われ、多くの国民が祝意を表します。こうした2月の行事は、寒さの中でも春への期待を感じさせ、また自然の移ろいとともに人々の暮らしや信仰が深く結びついていることを示しています。
「2月は逃げる」と言います。毎日嫌なことはたくさんありますが、これらの要因に負けずに学生と一緒に研究を推進したいと思います。