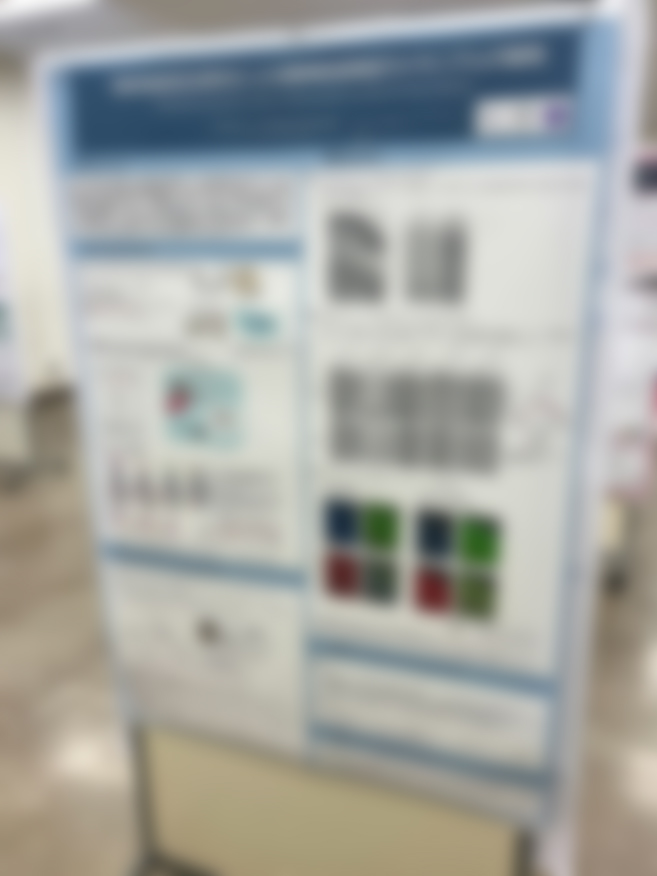2024年度の先導的研究者体験プログラム(ARE)の最終報告会が開催されました。6か月間の研究成果をまとめてポスター発表しました。事前に録画した1分間のショートプレゼンテーションに引き続いて、ポスター発表を行いました。私たちの研究室からは、S.N.さんとS.C.さんが発表しました。S.N.さんが最終報告会のレポートを作成してくれました。お忙しい中、対応ありがとうございました。先導的研究者体験プログラムは、早い時期から研究に取り組むことを支援するよい制度だと思います。医学類からは3件とのことだったので、来年度はもう少し増えればよいなと思います。
1. ARE 最終報告会の概要
開催日時・場所:1 月 20 日 / 3A204・3A207・3A209
プログラム構成(設営、ピッチ発表、ポスター発表)
10 : 10 ~ 11 : 25(2 限):設営(研究交流室 3A205 室ドア前に集合)
12 :15 ~ 13 :30 (3 限) :ピッチ発表(事前提出ビデオによる一人につき1分間の発表)
13:45 ~ 15:00(4 限):ポスター発表(奇数番号コアタイム)
15:15 ~ 16:30(5 限):ポスター発表(偶数番号コアタイム)
参加者:全 43 名
2.自身の発表
1 分間で自分の研究概要を説明した。異なる専門分野の方が多かったので、説明で専門用語を使わないように気を付けて作成した。自分の1分ピッチを聞いて、ポスターブースに話を聞きに来てくださった先生もいた。1 分で研究の背景・研究方法 ・意義と発展性 ・今後の展開まで詰めてしまったが、その先生から、「これらの要素を全部盛り込むよりも、この分野に興味を持った理由や、自身が面白いと思う部分など、詳細でわかりやすいイントロダクションを中心に発表するべきだ」とアドバイスをいただき、とても勉強になった。2つの部屋に、参加者全員のポスターが順番に並ぶように設置された。偶数 ・奇数でコアタイムが分けられており、私は奇数番号で前半だった。審査を担当しているらしき先生方も、生徒も自由に興味があるブースで話を聞くことができた。私のブースにも複数の先生が話を聞きに来てくださった。先生方からアドバイスや質問 ・感想を頂けた。ポスターの記載内容を自分の言葉で、適当な声量で説明できたと思う。1人、日本語が分からないので英語で説明してほしいという学生がいたため、できる限り頑張った。良い体験になった。
3. 他の参加者の研究・全体の印象
・他の発表者のテーマの傾向
高校から同じ研究テーマで研究している学生や、ARE2 年目、3 年目の学生の中には、実験結果や考察が出そろっている学生や、論文を執筆し終えた学生もいた。情報学群や理工系の研究内容は難しくていかにも理系という感じだった。人文 ・文化学群の学生は言語学習についての研究や、生物と文化の関りの研究、歴史の研究を行っていて、興味深かった。
・特に印象に残った研究
「尾張藩付家老成瀬家における…」という研究が特に印象的だった。実験してデータを集めて解析する理系の研究手法と違い、まだ世に出ていない歴史的な文書が、どこにあるかを史実から推定し、実際に足を運び、家主と信頼関係を築いて取得し、解読するという研究プロセスが面白いと思った。発表者が博識でわかりやすい説明をしてくれたことも印象的だった。
4. ARE 全体の反省とFuture Plan
テーマ設定、仮説設定のためのリサーチが非常に甘かったと思う。論文を読むときに、自分が欲しい情報だけを無意識に切り取ってしまって後で矛盾が生じたり、精読ができなかったりしたことで、研究の流れがつかめなかった。ARE によって学生同士の交流会に参加したり、発表したり、報告書を書いたりする機会を得られたことで、研究活動の基本的な流れを知ることができたのが良かったと思う。今年度の経験を生かして、来年度は頑張りたい。
生物学類2年 S.N.