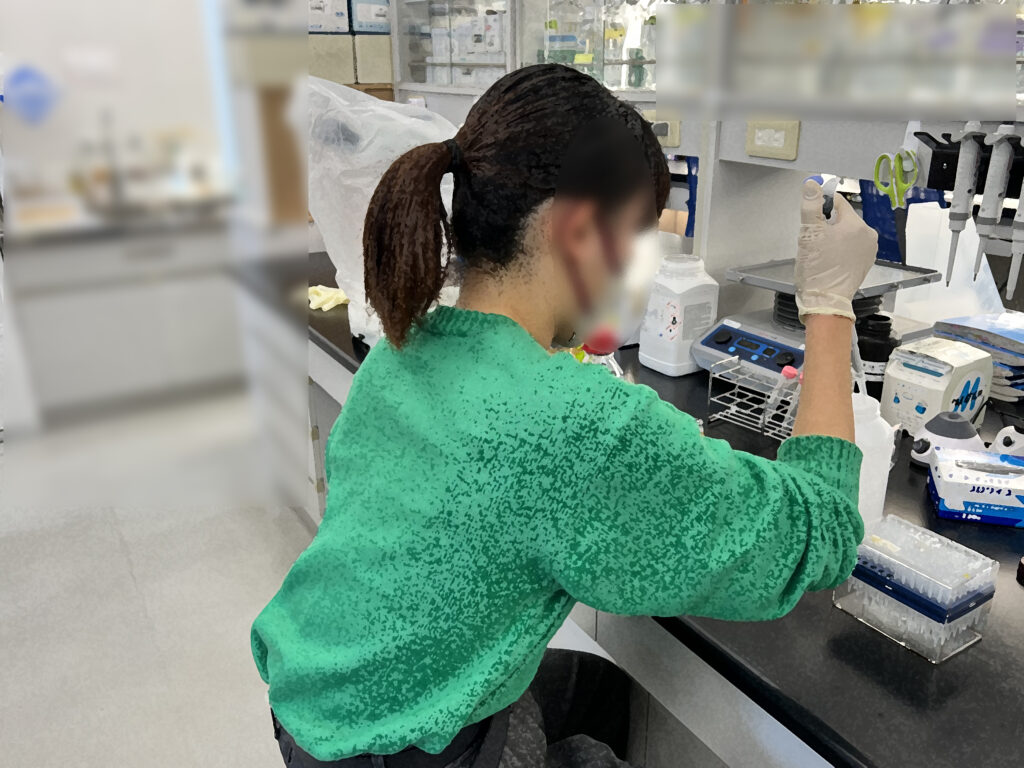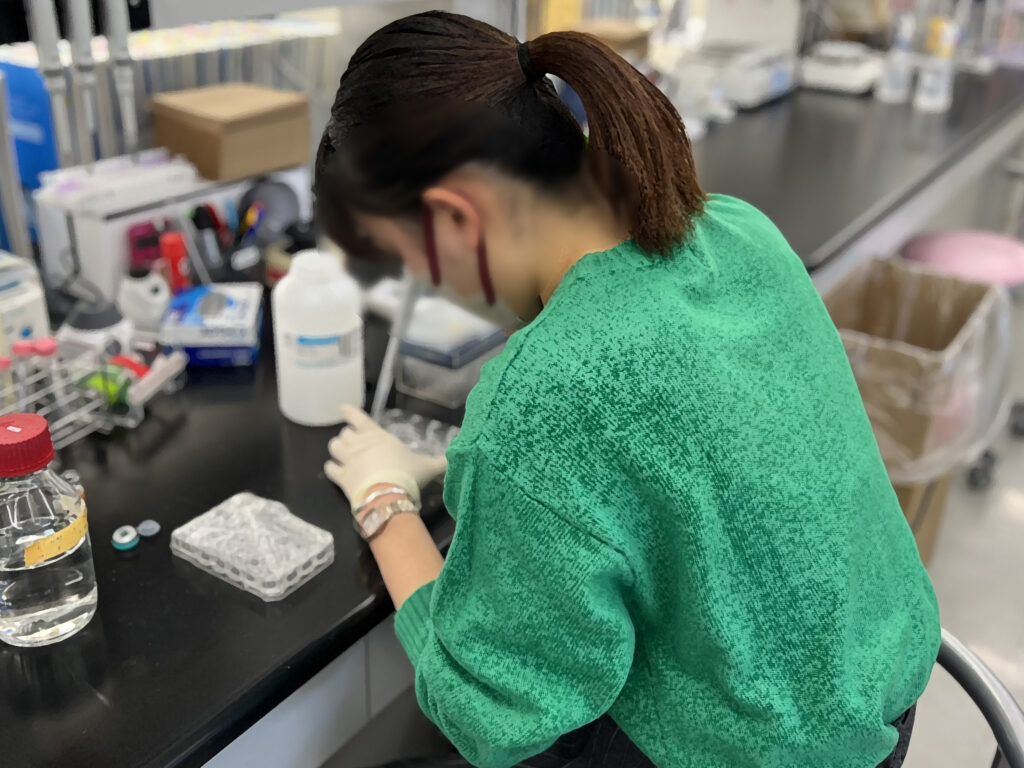医学類の学生の方とともに、研究会の準備と新しい実験の予備実験を行いました。2025年度がスタートすれば、▲▲講義や〇〇実習などで忙しくなってしまいますので、それまでに実験を進めたいです。
研究棟の近くで、スイセンの芽が成長しています。3月下旬の卒業式・修了式の時期には花が咲きそうです。モクレンとともに早春に開花する植物です。
スイセン(水仙)は、ヒガンバナ科スイセン属に属する多年草で、冬から早春にかけて可憐な花を咲かせる植物です。スイセンは中国を経由して奈良時代(8世紀ごろ)に日本に伝わったとされています。日本で最もよく見られる「ニホンスイセン(日本水仙)」は、実は地中海原産ですが、日本の気候によく適応しています。日本では古くから親しまれ、文学や文化の中にもその美しさが取り上げられてきました。
スイセンの学名である Narcissus は、ギリシャ神話の美少年ナルキッソスに由来します。彼は水面に映る自分の姿に恋をし、その場を離れることなく花となったとされています。この伝説により、スイセンは「自己愛」や「神秘」の象徴とされ、花言葉にも「清純」「希望」「尊敬」などの意味が込められています。
日本においては、スイセンは奈良時代に中国から伝わり、特に「ニホンスイセン」は日本の風土に適応し、各地で自然に広がりました。冬の寒さに負けずに咲く姿から、「忍耐」や「気高さ」の象徴ともされ、茶道の席や正月飾りにも用いられています。松尾芭蕉や与謝蕪村の俳句にも詠まれ、冬の風物詩として日本の文化に深く根付いています。
スイセンは冬から早春にかけて咲くため、「春の訪れを告げる花」として詠まれることが多いです。
松尾芭蕉(1644-1694)の俳句
「水仙や 白き障子の とも映り」
(スイセンの白い花が、障子の白さと共に映り込む美しさを詠んでいる。)
与謝蕪村(1716-1784)の俳句
「水仙の はなやかにして 暮れにけり」
(冬の夕暮れの静けさの中で、スイセンの花が凛として咲いている様子。)
スイセンは冬の寒さの中でも美しく咲くため、孤高の美しさや清廉な印象を与える花とされていました。
また、スイセンは観賞用の庭植えや鉢植えとしても人気があり、多くの品種が存在します。特に、香り高い品種は庭先に植えることで、冬の寒さの中でも芳香を楽しむことができます。福井県越前町では「水仙ロード」として知られる景勝地があり、一面に広がるスイセンの花が訪れる人々を魅了しています。スイセンの全草には「リコリン」などのアルカロイドが含まれており、有毒です。特に球根に多く含まれ、誤って食べると嘔吐や下痢、中枢神経系の麻痺を引き起こすことがあります。
スイセンは美しい見た目と優雅な香り、冬に咲く強さを兼ね備えた花として、世界中で愛されています。その可憐な花姿は、季節の移り変わりを感じさせ、人々に癒しと希望を与えてくれます。