「解剖実習を終えて」医学生からの言葉
解剖実習を通じた心の成熟
2025年度 医学類2年 F.T.
実習初日、実習室に入ると、ビニールに包まれたご献体が整然と並んでいて、衝撃を受けたのを覚えている。その時、私はまだ自分がご献体と向き合う覚悟と自覚がなかったのだと気づいた。その後、ネル布を外し、ご献体の顔を見た時、その方の生前の人生とご家族のことが頭に浮かんできた。その時、私はこれから6週間、ご献体やそのご家族が持つ「医療に貢献したい」という思いに応えられるよう、感謝しながら全力でご献体と向き合い、ご献体から得られる知識は全て得ようと心に決めた。その後6週間を通して、多くのことを学び、勉学の面でも精神の面でも成長することができた。
勉学の面で最も印象に残っているのは、人体構造を実感的に理解することができたということである。アトラスや教科書で予習してきたことが、解剖中に実際に目で見て、触れることによって「こういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間が多くあった。その瞬間ごとに、立体的な構造や臓器同士の繋がりを現実のものとして理解することができた。また反対に、アトラスと全く違うところから動脈が分岐していたり、あるはずの構造がなかったりと、頭で想像していたことと異なるということも多くあった。その経験から、人体の構造は一人ひとり異なるため、教科書に載っていることが全てだと思わずに、ご献体から得られる情報をもとに学ぶことが重要だと感じた。この経験は、医師として一人ひとり異なる人間を診るという基本的な姿勢を築くきっかけとなった。
勉学の面以外でも学んだことはたくさんある。その中でも、医学を学ぶ上で「周囲の人に感謝することの大切さ」を学べたことが心に残っている。解剖実習を通して、ご献体になることを決断してくださった方やそのご家族の意志の強さを痛感した。もし自分が家族の死に直面した時、快くご献体になることを勧められるかというと、自信を持ってできるとは答えられない。ご献体のご家族も同じで、たくさん悩んだ結果、未来の医療のためを思ってご体を私たちに託してくださったのだと思う。そう思うと、言葉にできないほどの感謝の気持ちと尊敬の念が込み上げてきた。今日の医療は、今までのような尊い意志を持った方々のおかげでここまで発展してきたのだと改めて感じた。将来、医療の現場で働く身として、常にそのような方々に思いを馳せて感謝しながら、精進していこうと思う。
最後に、ご献体いただいたご本人およびそのご家族、実習を支えてくださった先生方に感謝を申し上げます。この貴重な経験を胸に、今後も医学の学習に精進していきます。

協働と探究の六週間 ― 人とともに学び、からだに学ぶ ―
2025年度 医学類2年 A.T.
6週間にわたる解剖実習を終えて、実習前の自分より学術的、そして人間的に成長したことを実感しております。医学類に入学してからの今までの勉強は、講義を聞いて既知の事項を確認または暗記したり、それらを用いて実験したりするようなものが多く、どちらかといえば受動的な学習でした。一方解剖実習では手引書や資料はあるものの、手探りの状態で、自分で学びながら進めていくような能動的な学習です。教科書に書いてある内容がすべて正しいわけでもなく、血管の走行や筋肉の分布など、個人によって異なるものも多く存在します。それらを踏まえながら目的のものを探しているうちに気づきや学びを多く得ることができました。また、体の構造の共通点や相違点は非常に興味深いものでした。末梢の血管や神経の分布には多くのパターンが存在し、個人で大きく異なることもある一方で、生命維持にかかわるような中枢の部分の構造は違いが少ないことが多いということを学びました。将来臨床に出た際の、患者さんひとりひとりに寄り添った医療の必要性を身をもって感じることができました。精密でありながら、同時に臨機応変に大胆に働くからだと、それが維持する生命について学ぶことができました。実習を通して、体や生命についてより深く知りたいという気持ちが目覚め、今後の学習への意欲が高まりました。
また、解剖実習自体の特性や実習中の他の班員との協力によって人間的にも成長することができました。ご遺体を解剖させて学ばせていただくのは非常に医学教育として重要ではありますが、最初は慣れておらず、抵抗感や疲労感を感じました。実習を進めていくうちに、生命や死について、医学について、人生について深く考えさせられました。これらについて考えることは医療に従事するにあたって必要不可欠であり、将来の医療従事者としての責任感や使命感を感じることができました。また、班員と協力しながら作業を分担し、時には教えあい議論する経験も貴重なものでした。自分一人だと自信がないことも、切磋琢磨しながら共に学ぶ学友たちと協力することで深い学びにつなげていくことができました。何もかもを先生に聞いて受動的に学ぶのではなく、自分で課題を見つけ、今まで学んできたことを踏まえながら考察を重ね、議論を通して学びを深めていくプロセスが刺激的でした。今後の学習の指針としたいと思います。
このような経験をさせてくださった、ご献体くださった故人とそのご家族の尊い意思に非常に深い感謝の念を表すとともに、故人のご冥福をお祈りいたします。

解剖実習を終えて
2025年度 医学類2年 M.K.
解剖実習が始まる前、私は期待と不安が入り混じった感情を抱えていた。緊張はしていたものの、覚悟はできているはずと言い聞かせていた。しかし、実際に初めて解剖室に足を踏み入れた時、今までに経験したことのない独特な空気感に圧倒されたことを覚えている。実習台を目の前にして医療倫理について時間をかけて学ぶ間にも緊張が途切れることはなかった。ご献体のネル布を開けて手足に包帯を巻く時、手のひらに触れた瞬間に、ご献体いただいた方が生前触れた人や物に思いが及んで言葉にできない重みを感じた。私には死を身近に感じた経験はほとんどなかったが、これからたくさん向き合っていく死を考える大きな一歩になったと思う。目の前の「先生」だけでなく、送り出してくださったご家族や社会全体の思いの上に今の学びが成り立っているのだと責任を強く感じた。
実習中は予復習の難しさに何度も直面した。前日にアトラスや手引き、実習書で時間をかけて準備しても、実際のご献体と向き合うと、頭で描いていた構造とはまったく異なっていたからだ。座学では知り得なかった人体の一つひとつの構造の個別性を身をもって体験した出来事だった。
また、同じ実習班の仲間と協力し合いながら学びを深められたことも、忘れがたい経験となった。アトラスを見せ合い、疑問を共有し声を掛け合いながら剖出を進めたことで、医療を支える協働の大切さを学んだ。精神的にも肉体的にも楽ではなかったが、だからこそ一緒に取り組んだ時間が印象深く残っている。
解剖実習の最終日は、最終試問と納棺式が続いて行われた。ネル布とビニールで丁寧に包ませていただいていると、初日にネル布を開けたときの光景が頭をよぎった。目の前にあるご献体の姿はその時とは全く違っていて、それだけの時間をかけて学ばせていただいたことを改めて実感した。
納棺式の前夜、果たして私は先生であるご献体から余すところなく学びきることができただろうかと考えた。正直に言うと、気持ちに反して、知識や技術の未熟さを感じた場面ばかりが思い出され、悔しくなった。それでも、こうして得た学びをどう生かしていくかが自分のこれからに問われているのだと思う。人の体は繊細でありながら複雑に保たれていて、知識だけでなく、命と向き合う姿や医師としてどう在るべきかなど多くのことを学ばせていただいた。これから先、一人ひとりの命と誠実に向き合えるよう努力を重ねていきたい。最後になりますが、ご献体くださった方、そのご家族、そして実習に関わってくださったすべての方に心より感謝申し上げます。貴重な学びの機会をありがとうございました。

解剖実習を終えて
2025年度 医学類2年 Y.U.
解剖実習は、医師を目指す上で最も重要な過程の一つであり、入学前から強い期待を募らせていた。実習の初日、緊張感とともにビニールとネル布をめくりあげてご遺体と対面したとき、今からこのご遺志に報いることができるよう一つでも多くのことを学ばなければならないという思いに駆られた。はじめのうちは責任感が重く、興味本位で勉強をするのではなく、学ばせていただくという意識で解剖実習の期間中を過ごしてきた。
実際にご遺体に向き合ってみると、あまりの構造の複雑さに圧倒された。本物の人体は、教科書やアトラスなどに書かれた平均的な構造に当てはまらないことがほとんどであった。例えば、静脈が左側にあったり、両側の卵巣静脈が腎静脈へ派生していたりしていた。他の班のご遺体を観察させていただいても、血管の太さ、走行、脂肪の量、臓器の大きさ、病気の有無など、誰一人として同じではなかった。これから学んでいくことは、生物学のように体系化された理論だけを追求するだけでなく、個性があるものに向き合うものなのだろう。
実習では悪戦苦闘しながらも、器官や組織を目で見たり、自分の手触れで確かめたりした経験が血肉となり、臨床の現場において大いに活きるだろう。解剖学のカリキュラムを一通り終えただけでは、一人一人個性がある患者さんを理解できるレベルには到底達していないと感じている。実習が始まる前よりも、むしろ分からないことが増えたように思う。解剖学には終わりがなく、生涯を通して学び続けるものなのだろう。
最後になりますが、医学の発展に寄与するという崇高なご意思のもとお身を託されました故人とそのご遺族の皆様に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。そして、実習が円滑に進むようご準備いただき、ご指導を賜りました先生方並びに技術職員の皆様、共に学んできた班員の皆様に厚く御礼申し上げます。

解剖実習を終えて
2025年度 医学類2年 A.S.
「亡くなったら何もできないし火葬されちゃったら骨しか残らないけど、亡くなった後も自分の体を使って学んでもらえたら、余す所なく生きた感じがして良いね」
解剖実習が始まってすぐ、母が言っていた言葉だ。私はこの言葉にハッとさせられた。「故人は私たちに学んで欲しくて、献体になるという決断をしてくださったのだ」と。解剖実習が始まったばかりの頃、ご遺体を解剖することに対し私は何か後ろめたさや恐怖のようなものを感じていた。授業の一環であり、法に触れることはないと分かってはいたが、専門的な医学の知識や技術もない我々が、本物の人体にメスを入れることなど許されるのだろうか、と。しかしこの言葉を受け、私を縛り付けていた「何か」が解かれた。専門的な医学の知識もない我々だからこそ、分からないながらももがき、その過程で多くのことを学んでもらうために、故人とそのご家族はご遺体を提供してくださったのだ。そんなご献体の尊いご志志に与り、少しでも多くのことを学ぼうと、6週間貪欲にもがいた。
人工知能や科学技術が発達した今日、本物の人体でなくても解剖実習はできるのではないかという意見もあるかもしれない。しかし、6週間の解剖実習を終えた今、やはりこの解剖実習には意味があるのだと私は思う。血管の分岐や筋肉の大きさは個体差があり、教科書やアトラスとは全く違う。起始停止や位置関係、その人の持っていた疾患を総合的に鑑みて同定を行うというのは、教科書を超えた学習であり、これはやはりこの世界を「生きた」故人からしか学べないことだと思う。また、医師としての自覚をもつという意味でも重要なのではないか。何にも変えることのできない1人の人間のご遺体を解剖させていただくというのは責任の大きなことであると同時に、自分のまたは大切な人の身体を提供してまでも我々に学んでほしいと、様々な人が期待してくださっているのだと身が引き締まる思いがした。
6週間の解剖実習を通して得たのは、単なる解剖の技術や知識だけにとどまらない。チームで協力して作業を行う協調性、毎日朝から晩まで立ちっぱなしで解剖を行う体力と集中力、思うようにいかなくても諦めない忍耐力、日々学んだことを復習し明日の実習に備えて予習をする勉強の習慣ーー。答えのない問いに向き合い、目先の試験のためではない学習をするという、今までの「勉強」とは明らかに異なる学習をした。間違いなく私の人生の中で最も濃い6週間であり、信じられないほど多くのことを学び、成長した。言葉では尽くせないこの全てが将来医師になる上でのかけがえのない学びであり、糧になると確信している。
最後にはなりますが、本実習を遂行させてくださった全ての方々に心より感謝申し上げます。ご献体いただいた故人とそのご家族、先生方、先輩方、職員の方々、本当にありがとうございました。

解剖実習を終えて
2025年度 医学類2年 Y.I.
1か月半の解剖実習が始まる前は、ご遺体を解剖することに対する不安があったが、それと同時に、実際に人体を見られることに対して強い関心を抱いていた。教科書を見ながら、実際の人体がどうなっているのだろうと、貴重な時間を過ごせることへの感謝を感じていた。
実習1日目、解剖室で白い布に覆われているご遺体を前にして、私はそれまで考えなかったご遺族の方や故人の思いを想像し、緊張を感じることになった。献体をしてくださる故人の尊い意思に対して考えが及ばなかった自分を恥じ、深い感謝の気持ちを常に持ちながら実習に取り組むようになった。
実習の時間は驚くほど速く過ぎていった。帰宅してからは就寝するまでアトラスや手引きと向き合い、実習室では先生であるご献体と向き合う生活が続いた。毎日アトラスと実習の手引きで予習と復習を繰り返しても、複雑な人体の一部分しか理解し習得できないことを実感し、非常に悔しく思った。機能や臨床と結び付けた学びは無限にあり、疑問は次々にわき、人体の面白さ、複雑さ、精巧さを毎日実感した。ご献体から学ばせていただける時間を無駄にしてはならないと熱心に勉強し続け、気が付けば休憩時間も実習室で構造を観察するようになった。
解剖をするなかで、自分の学習をもとに想像していた構造と、実際の構造が異なっていたことに驚いた。耳や腎臓などでは、肉眼では判別できないほど小さな構造の中に、複雑な機能があることが非常に不思議で、人体のつくりの精巧さに感動を覚えた。思えば解剖実習は驚きの連続であり、実際に目で見ることでしか学べないことが多くあった。個人によって体のつくりが異なるということを学べたのも貴重な経験であった。動脈の分岐、筋肉の発達具合などはご献体によって全く異なっており、ご献体が単なる人体ではなく、故人の生活、人生を強く映し出しているように感じた。自分が将来向き合うのは人体ではなく一人の人であり、治療法も一人ひとりによって異なること、患者さんを理解する重要性を学んだ。
解剖実習の最終日、初日とは全く異なった姿になったご献体を見て、多くのことを学ばせていただいたことに対する感謝を強く感じた。また、故人やご遺族の方々がご献体を決意なさった背景には、将来多くの患者さんを救ってほしいという医師に対する思いや期待が込められていることを感じ、責任を自覚した。1か月半という短い時間だったが、記憶に鮮明に残り続けるであろう、貴重な時間だった。
最後に、ご献体してくださった故人、ご遺族の方々に、貴重な経験をさせていただいたこと、感謝申し上げます。将来医学に貢献できるよう、精進いたします。

解剖実習を終えて
2025年度 医学類2年 A.F.
解剖実習は、医学生としての私の意識を大きく変えた体験でした。これまで、医学類に入学してから基礎医学のコースで様々なことを学んできましたが、その多くは教科書や授業試料に書いてある『事実』を学ぶことにとどまり、実習も「結果を予測し、指定された実験手順に従ってデータをとり、なぜそのデータが得られたか考察する」という形態が主でした。しかしそれらの経験を愚直に当てはめても解剖実習では歯が立ちませんでした。
実習初日、張り詰めた空気の中でご献体のビニールを開けたことを覚えています。そこにいたのは「人」でした。生きた証が感じられる肌のしわ、いまにも開きそうな目や口を見て、今から人の体にメスを入れるのだと自分が選んだ道の険しさを思い知りました。
そこからの6週間はめまぐるしく過ぎていきました。少しでも早く起きて実習書やアトラスで予習・復習し、その日の流れをイメージし、休み時間も放課後もご献体と向かい合いつづけ、気づけば0時を過ぎている、そんな日々の積み重ねでした。しかしいくら勉強しても手順通りうまくいくことは稀でした。ご献体にそれぞれ変異や見た目の違いがあり、目的の神経や血管が見つからない焦り、保存すべき構造を壊してしまった挫折などで徐々に追い詰められていました。実際の人体は一つとして同じではなく、決して教科書通りにはいかないという厳しさを味わいました。この教訓は将来医師として働く中で何度も感じることになるのだと思います。
厳しさの一方で、人体の精密さに感動もありました。どういった発生で今の構造ができ、各器官がどこでつながり、どのように協調し、時として疾患となるか。それをただ教科書で読むのではなく自分の目で見る体験は、一生に一度の大変貴重なものでした。頭蓋からの迷走神経が喉頭や心臓に枝を出しつつ腹部につながること、心尖と肝臓・横隔膜の位置関係など興味深い構造を学ぶのに6週間ではとても足りないと感じました。また、腎臓の断面を見て基礎医学で習ったネフロンのミクロな構造と肉眼で見たマクロな構造が繋がり、今までの学びがより臨床に近づいたように思いました。
解剖実習を通して、ご献体から本当に多くを学びました。解剖が進むにつれ、ご献体が初日の「人」の姿から構造としての「ヒト」になっていくのを感じ、黙祷のたびに「この方はどんな思いで献体くださったのだろう」と想像していました。納棺の日、棺に書かれたご献体のお名前を見て、ご本人やご家族の思いをあらためて感じました。 このような貴重な学習機会は、それを支えてくださった先生方、技術職員の方々、先輩や友人、そして何よりご献体とそのご家族おかげで得られたものであり、心より感謝いたしますとともに、解剖実習で得た知識と経験をもとにより一層医学の勉強に励みたいと思います。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 O.M.
解剖実習初日、初めてご献体にメスを入れたとき。今まで一度もメスを握ったことのなかった私は、ご献体のお顔の目の前で初めてメスを持ち手が震えた。あのときの言葉に表すことができない不思議な気持ちを忘れることはできない。毎日実習室に行き剖出を進めるにつれて、ご献体は「 人」というより「 対象」のようになっていった。目的の組織や構造を観察するために、脂肪や結合組織などを上手に取り除くことができるようになった。メスを使うことへの抵抗もなくなり、継続すればどんなことにも慣れ、どんなことでもできるようになるのだと感じた。しかし、初日に感じた気持ちをふとした瞬間に思い出すことがあり、私は医学生として人体解剖をしていて将来医師になるのだ、と実感させられた。実習期間中、残しておくべき構造を誤って失ってしまうことが何度もあったが、将来手術を行うときのこ
とを考えると少し怖くなった。自分の手の動きの1ミリのずれが、最悪の場合患者さんの命を奪うことにもなるのだと身をもって実感した。
手の解剖をしているとき。皮を剥ぎ、脂肪などを取り除き、筋肉や神経の走行を観察した。私は右手でメスあるいはピンセットを持っていたが、左手をご献体の手の甲に添えて剖出を行った。このとき、ご献体は少し前まで生きていらっしゃった「 人」であると強く感じた。心なしか手の温かさを感じ、まるで母や友人の手を握っているかのような感覚だった。ビニールとネル布を開いて初めてご献体と対面したときよりも、ご献体が「 人」であるという感覚を強く感じた。人は死を迎えても人なのだと思った。解剖実習は私にとって死と向き合う機会にもなり、死というあまりに未知なものに対する恐怖は少し薄れ、それ以上に生命がいかに尊いかを実感した。
納棺のとき。手の解剖をして以後、胸腔「 腹腔を開き、頭部を離断し、あらゆる構造を取り除いたため、ご献体は最初の姿とは大きく異なったものになっていった。また、6週間にわたり毎日解剖を行い、私に慣れと余裕が生まれ、人体解剖をしているのだという感覚が薄れてしまっていた。しかし、最終諮問を終え納棺の時がやってくると、私の感情は再び大きく動いた。体の各構造をできるだけ元あった状態にして、ビニールと布で丁寧に包み、ご献体を棺に納めたとき、ご献体いただいた方も1つの人生を歩んだ「 人」なのだと心から実感した。そして、大切なお体を私たちの解剖実習のために捧げてくださったことに対し、感謝の気持ちでいっぱいになった。
ヒトの体の中は私が教科書で学んでいたものとは全く異なり、想像していたよりも遥かに複雑で緻密だった。6週間の解剖実習で、人体の構造が非常に精巧であること、受精と発生から始まるいくつもの奇跡が重なって1人の「 人」が出来上がるということを学んだ。解剖実習を終えた今、これから人体や医学についてさらに学びを深めたり医療に関わったりすることが楽しみである。ご献体いただいた故人とそのご家族はもちろん、解剖実習を通して関わった友人、先輩方、先生方、また実習の準備や管理に尽力してくださった方への感謝の気持ちを忘れずに、医学生そして将来は医師として、医学や医療に真摯に向き合っていこうと思う。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 U.A.
解剖実習最終日、ご献体をネル布とビニールでそれまでで一番丁寧に包み、棺に納めてお布団をかけたとき、私は安堵の気持ちでいっぱいになった。それは、大変な解剖実習を無事に終えたという思いもあるが、それよりも、この方はやっと安らかな眠りにつけるのだという思いの方が強かった。
初日に実習室に足を踏み入れた時、まず整然と並べられたビニールに包まれたものが、異質な存在感を放っていると感じた。ネル布を初めて開いたとき、つい2年前の祖母の葬式を思い出していた。そこで見た棺の中の祖母の顔と、ご献体の顔の様子が違ったことが、なんだか申し訳なかった。だからこそ、最初のうちはご献体の生前を考えないようにしていたのではと、今は思う。しかし、解剖実習を進めていくにつれて、その思いも変わっていくようになる。足の筋肉を解剖しているとき、班員が「この人は、ご高齢なのに足の筋肉が大きくてしっかりしているね。最期まで歩けていたのかな」とつぶやいた。また、取り出した肺に固い膜が付着しており、それが空気中の粉塵やほこりを長く吸っていたことによるものと知ったとき、班員とどこに住んでいたのか、すごく長く生きていたのだねという話をした。こうして班員と話しながらご献体と向き合っていくうちに、ご献体の生前に思いを馳せるようになり、この方も生きていたのだと感じるようになった。それに伴い、ご献体してくださった方の生前の偉大な決意と、ご遺族の方の思いを実感し、感謝の念を感じるとともに、この実習期間中にできるだけ多くのことを学び取らせてもらおうと思った。
実際、この解剖実習では本当にたくさんのことを学ばせてもらった。臓器や筋肉の立体的な位置や、それぞれの血管の太さや関係、走行など、実際に手を動かして感じるものは、決して座学だけで得ることはできなかった。人体は組織としても仕組みとしても本当によくできていて、剖出しなかった細い血管ひとつひとつにもその役割があることを感じた。そして、人体は人によってまったく異なるということも、実習を通して嫌というほど理解できた。神経の走行一つとっても、正確な位置を定めることはできない。これは私たちが実際に医療に携わる中で、患者さん一人ひとりに適切な医療を提供するために、気を付けていかなければならないことだと考える。反対に、個人差という言葉に甘えず、普遍的な知識も身につけていかなければならないと、剖出をスムーズに進める先生方を見ながら、そう考えた。
納棺するときに思い出していたのは、やはり祖母の顔だった。祖母とかなり異なる様子の納棺を見て、私は改めてご献体の方とご遺族の方々の意志に感謝した。貴重な学習の経験をくださったことに感謝し、この学びを糧に必ず立派な医師になると誓った。
改めて、ご献体くださった故人の方とそのご遺族の方々、実習を支えてくださった先生をはじめ、ご協力くださったすべての方に感謝申し上げます。そして、ご献体の方の安らかな眠りを心よりお祈り申し上げます。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 S.M.
長年バレエを習っていた私にとって、上肢や下肢、背中の筋肉の解剖は非常に興味深い体験であった。バレエは全身を使って表現を行う芸術であるからして、表情のみならず頭の先から足の先までの筋肉や関節を意識的に使うことが要求される。解剖が進むにつれて常日頃イメージしていた筋肉の走行やまとまりが確かな実感を伴って目の前に現れることに感動を覚えた。体表から観察できるもののみならず、美しい筋肉の中に神経や血管が一定の規則をもって緻密に存在する様は、精巧な機械のようで圧巻であった。
一方で、胸腔及び腹腔の解剖に入ってからは多くの困難に直面した。私が解剖させていただいたご遺体には上行結腸、子宮、胆嚢がなかった。肝臓はがんの転移により肥大し、腹腔上部に存在する臓器を圧迫しており、腹腔下部の臓器はがんの播種が広がり癒着により正常構造をとどめている部分はほとんど存在しなかった。
当初は手持ちのアトラスと全く異なる概観に非常に困惑し、いただいたご遺体から何を学ぶべきか見当もつかなかったが、その後、このご献体から学べることが非常に多いことに気が付けた。正常の構造や位置関係は他のご遺体や教科書を参照させていただけるが、癒着の状態やご遺体に施された手術はこのご遺体でしか学べないものであると気が付けた。腹膜を破った後からは自己学習として、結腸右半切除術とは何か?がんの転移経路は何か?癒着はどうして起こるのか?もしこの患者さんを手術するとしたらどうやって視野を確保しようか?などを調べたり自分で考えてみたりと、解剖して得られる情報と知識とのすり合わせを自己学習として深めることができた。この経験は医師として患者さんに触れあうようになったときに大きなアドバンテージになると思う。
習い事の知り合いの方から、ご献体に対する興味深いエピソードを聞いたことがある。彼女の母親は自分の身体を医学の発展にささげることを強く望んでいらっしゃったのだが、がんで亡くなったことで死亡時にはとても瘦せてしまわれており、友人は学生さんにこの状態のご遺体を提供することは忍びないとしてご献体を行わなかったそうだ。解剖実習を行う前は私もこの意見には同意していたが、今となっては全くの反対である。
痩せて衰えてしまった筋肉も、癒着により視野の確保が難しい腹腔内もご献体の方が病気と闘った大切な証であり、我々医学生はそこから教科書で得られる以上の何かを学んで肥やしにすることができる。多種多様な病歴や、奮闘した証を持った方がたくさんご献体くださるようになれば嬉しいな、というのが解剖実習を終えて最も強く感じた感想である。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 U.S.
6 週間にわたって行われた解剖実習は、本当にあっという間であった。毎日ご遺体と向き合ってアトラスとにらめっこをする日々が続き、精神的にも体力的にもつらいと感じることが多かったが、医学生として非常に貴重な経験をし、多くのことを学ぶことができたと感じている。
実習初日、解剖室へ足を踏み入れると少し寒気がした。ご遺体がずらっと並んだ光景は衝撃的で、ついに解剖実習が始まるのだという緊張感から思わず無言になったのを覚えている。解剖を始める前に全員で黙祷をささげたとき、「故人とその家族の尊い意思に感謝して」という言葉を聞いて、その意思を決して無駄にしないよう最後まで目の前のご遺体に真摯に向き合おうと心に決めた。
いざ解剖が始まると、人体の構造の複雑さと個体差に驚かされた。筋肉や神経などは脂肪組織に埋もれていて剖出しづらく、さらに教科書やアトラスで予習したものとご遺体とでは異なる部分が多くて同定すること自体が難しかった。しかし、筋肉の起始や停止、血管・神経の走行、それらの立体的位置関係を観察し、どの筋肉をどの血管が栄養していてどの神経が支配しているのかを班員と議論しながら把握してくうちに、その機能を包括的に学ぶことができた。また、ご遺体ごとの個体差は大きく、他の班のご遺体と比べると、筋肉や臓器の形・色・大きさが違っていたり、血管や神経が別の箇所で分岐していたりしていて、実際にひとの身体を扱うということはこういうことなのだと実感し、非常に興味深かった。他にも、この解剖実習を通して学んだこととして、協力して助け合うことの重要性も挙げられる。約 1 ヶ月半という長い期間、毎日何時間も解剖を行っていくなかで、時には班員と意見が対立することもあった。しかし、班で相談しながら、分担した役割を各々が果たし、前日の進捗状況や情報を共有することで、実習を円滑に進めることができた。納棺の際に感じた達成感と班の一体感は、今までになく大きなものであった。改めて振り返ると、ただ教科書で人体の機能と構造を勉強するのとは比べ物にならないほど多くの知識や感覚を得ることができた。目の前のご遺体が先生であると先生方がおっしゃっていたように、ここで学んだ解剖学的知識は将来臨床の場で必ず役に立つであろう。解剖実習を通じて、医学を学ぶことに対する責任とひとの身体を扱うことの重みを感じ、医学生としての大きな一歩を踏み出したように思う。この経験とご献体くださった方への感謝を忘れず、自分が目指し理想とする医師になれるよう今後も精進していきたい。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 S.M.
解剖実習に取り組んだ6週間は人生の中でも一番密度の高い期間だった。これほどまで感情が動いた実習はなかったし、日々変わり続ける体調や心情の中、同じことに取り組み続ける6週間は初めての経験だったと思う。
解剖実習初日。初めてご献体と対面する瞬間の緊張感は今でも鮮明に思い出すことができるくらいに凄まじいものだった。私だけでなく、周りの同期も同じように緊張していたのか、実習室全体が異様な空気に包まれていたのを覚えている。そこから中間諮問までの3週間弱、手引き通りに剖出を進めることに夢中になりすぎて、各々の構造の関係性やその構造が存在する合理的な理由を考える余裕さえもなかった記憶がある。そのくらいギリギリの状態ではあったが、実習の最初と最後の黙祷の時は一度心をリセットしてご献体に向き合うことによって神聖な気持ちを感じることができたと思う。
中間諮問のあった週に私が体調を崩してしまい、一日実習を休んでしまったことがあった。休んだ日に実習が円滑に進まなくなるだけでなく、中間諮問という一つの大きな区切りを前にして、進捗が大幅に遅れてしまった。そのことによって班員には本当に迷惑をかけてしまったと感じているが、班員はそんな私を咎めることなく、純粋に体調を心配してくれたし、復帰後も無理のない範囲でやってくれればいいよと気遣ってくれたのが本当にありがたかった。このように、ご献体に向き合う以外にも周りの人と毎日協力して剖出を行わなければいけない環境下で絆が生まれたのも事実だと思う。班員の中には今までほとんど会話をしたことのなかった班員もいたが、解剖実習を通してたくさんコミュニケーションをとり協力して実習を乗り越えることができたのは今後の財産になると思う。
中間諮問を終えると、腹膜を切開き臓器の剖出をし始めたが、そのころになると徐々に各構造の関係性を意識して勉強できるようになってきた。それからはより一層ご献体の神聖さを感じることが増えてきた。人間の体は一つとして同じものはないし、教科書通りの構造が必ずあるわけでもないということが改めて感じることができたし、教科書ではあるはずの構造の機能を補完するために発達している構造を見つけるとさらに一層理解を深めることができた。
このように充実した解剖実習を行うことができたのは、ご自身の体を提供してくださった方やそのご遺族の意思があってのことであると思う。解剖実習を経るとその気持ちがより強くなった。ご献体と向き合うことを通じて、医学的な知識の理解を深めるだけでなく、人としても成長したと感じることができたため、本当に実りある実習であったと感じた。
最後に、ご献体くださった方、そのご遺族の方、本当にありがとうございました。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 I.M.
私は、医学部に入学当初から自分に解剖ができるのだろうかと解剖実習に緊張していた。あっという間にM2に進級し、解剖実習が近づいてくるにつれて、緊張や不安も増していった。とうとう迎えた実習初日に実習室に入ると、すでに実際にご献体が各実習台に並んでおり、いよいよ始まる解剖実習にとても不安を覚えた。しかし、いざご献体と対面すると、ご献体された方の意思を無駄にしてはいけないという気持ちが強くなり、解剖が自分にできるのだろうかといった不安は無くなっていった。実習が始まると、学ぶことに必死で、あっという間に6週間にわたる解剖が進んでいった。解剖が進み、実習が始まる前に感じていた不安や緊張は無くなったが、メスを入れる際は緊張感を持って解剖に挑んだ。初めは加減が分からずなかなか上手く解剖できないことも多かったが、先生方から教えていただき、手技を身につけることもできたと感じている。6週間毎日のように教科書やアトラスで予習、復習をし、解剖に挑んだが、予習でみたように簡単に組織を見つけることはできなかった。筋肉や臓器は実際の人体では教科書やアトラスの図とかなり異なっているものも多く、ご献体によっても様々で、印象に残った。一方で、動脈や神経は走行や分岐がほとんどアトラス通りになっているものも多く、人体の精密さを実感し、逆に衝撃を受けた。このように、この6週間の実習を通して、実際に自分で解剖を行わなければ気がつけないような人体の仕組みを理解することができた。また、今まで学んできたことを実際にご献体で確認することもでき、とても有意義な実習となったと思う。これから学ぶ際もご献体を思い出すことで、学びを深めていきたいと思うとともに、これからの学習にもより一層力を入れていこうと緊張感も覚えた。
今までの学習は基礎的な内容が多く、実際の人間について考えることは少なかったが、解剖でご献体と向き合う中で、実際に人間と対面し医学生としてようやくスタートを切ることができたように感じた。また、班員と6週間にわたって協力して解剖を進めていくという体験は、他ではすることのない経験であり、人間としても成長することができたのではないだろうか。実習が始まる前はあれだけ不安と緊張を抱えていたが、そんな実習をやり遂げることができ、大きな達成感と成長を感じた。
今回、この貴重な経験をやり遂げることができたのも、ご献体くださった方やそのご家族、先生や先輩方など、多くの人の支えがあってこそであった。最後に支えてくださった方々と、ご献体くださった方とそのご家族の尊い意思に心より感謝申し上げます。

解剖実習を終えて
医学類2年 K.F.S
解剖実習初日、大学入学前から解剖学に興味があった私は、初めて身近に死を感じる緊張 とともに、少しの好奇心を感じていた。これまでしてきた座学とは違い、実際の人体に触れながら学ぶことができる機会を素晴らしい機会であると感じていた。周りの友人は「死」に向き合うことに緊張し、実習室に入ることを躊躇している者もいたが、私は好奇心に押され、実習室に足早に入っていった。実習室に入って初めに感じ、目にしたのは、空気の冷たさ、嗅ぎなれないホルマリンのにおい、そして解剖台の上のビニールにつつまれたたくさんのご検体である。明らかに異様なその光景に、私は怖さを感じた。ほかの人はこの光景を想像して怖がっていたのかと思うと同時に、「死」と向き合うことを深く考えられていなかった自分に気づき、情けなさを感じた。普段生活している中で目にする多くの人々。この人々はもちろん生きていて、自分で動いていて、話をしている。そんな「人」が布で巻かれて動かないのは、寂しさや違和感を覚えざるを得なかった。私が勉強させていただくご検体の前に座り、先生方の説明を聞いている間、ビニールにつつまれたご検体を近くで見ると、ひざの関節や腰、頭などの輪郭がわかり、改めて目の前にいらっしゃるのは今まで生きていた、私たちと同じ「人」なのだと実感した。
初めの作業は、ご検体の皮切だった。今まで人の皮を切ったことはない。誰しもそうだろう。皮切のためにメスを入れるとき、全員が緊張していただろう。慎重に、ご検体、そしてご遺族の方々に失礼の無いよう、作業は進んでいった。初めは人体のことを理解していなかったこともあり、脂肪が十分に残っている段階から、丁寧に神経を探っていた。この時の私は神経がどのくらいの強度なのか、どんな色をしているのか、どこからどこへ走行しているかもわかっていなかった。解剖実習を終えた今では、丁寧に作業することも大切だが、ご検体をリスペクトするということはご検体からたくさんのことを学びきることであると考えている。そのため、実習中盤までの私にはご検体や遺族の方々をリスペクトで来ていなかったと感じている。実習中盤までは、実習書に記載されている構造物をひたすら探して見つかったら次、見つかったらまた次、、のように作業として実習を行っていた。学びはあったもの、課題のようになってしまうやり方に、私は実習前のような好奇心を感じられなくなっていた。これは自分にとって良くないことであるのはもちろん、私たちのために協力していただいたご検体、そのご遺族にとても失礼なことである。中間諮問や実習前のレクチャーで指摘されて自分が愛の無い解剖を行ってしまっていたことに気が付いた。中間諮問後の胸腔、腹腔について勉強させていただくフェーズでは、この反省を生かして、どの構造物がどこにあるかだけでなく、なぜそうなっているか、そこにあることでどのような役割を果たしているかなどを考えながら実習に励むことができたのではないかと思う。
実習が終了し、納棺させていただくとき、私の心は感謝でいっぱいだった。ご検体なしでは学べなかったたくさんのことを、実際に見て、触って、考えて学ぶことができたからだ。医学類に来なければできなかったこの貴重な体験を大切にして、ご検体やそのご家族への感謝を忘れずに、これからの学習に生かしていくことも、ご検体へリスペクトを示す方法の一つである。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 飯田拓海
医学の道を志した時から、そして実際に医学生としての生活が始まってからおよそ一年、幾度となく耳にして来た解剖実習を先日終えた。解剖実習を行なった約一ヶ月半は決して容易いものではなかったが、私のこれからの人生にとってかけがえのない経験となった。
解剖実習の開始が近づくにつれ、自身が医学の道に進むことへの覚悟を感じるとともに、実際に解剖実習を行うことへの不安も感じていた。そう感じているのも束の間、解剖実習の開始日を迎えた。普段の雰囲気とは異なり、緊張感に包まれたロッカー室を出て実習室に入り、布とビニールに包まれて並んだご遺体の前で席に着いた。“御献体いただいた故人と、そのご家族の尊い意志に感謝して、黙祷”という先生の言葉で実習室が静まり返り、感謝の意を抱きながら深呼吸をして目を開いた。いざ実習開始となり、ご遺体にかかったビニールを外したが、その瞬間は、失礼ながらお顔を直視することができなかった。少し時間を取り、気持ちを落ち着かせて改めてお顔を拝見すると、ご遺体は想像していたよりもずっと穏やかで、暖かな表情をしていた。改めてご遺体への感謝の気持ちを持ち、解剖実習を行う日々が始まった。初日から最終日まで学びの日々が続き、実習が終わればその日行った内容の復習、翌日の内容の予習をして翌日の実習に臨んでいた。自分で学習して実習に取り組んでも、教科書とご遺体が完全に同じであるはずもなく、先生方に教えていただきながら実習を行う日々が続いた。学習ペースについても手探りだったが、日々の学習、実習の中で着実に知識がついていくのを感じたほか、手技も経験を重ねることで向上していった。開始当初は不安や緊張感が大きく、剖出を行うので精一杯だったが、試問が近づく頃には慣れてきたこともあり、他の班の御献体との病気などによる違い、そしてその原因など、少しずつながらも考えを深めることができるようになった。限られた期間の中で全てを学ぶことは難しかったが、先生の“皆さんの本当の先生はご献体である”という言葉を胸に、御献体から非常に多くのことを学ぶことができた。長いようで気づくと過ぎてしまった六週間の解剖実習を通し、果てなく長い医学の道への小さくとも力強い一歩を踏み出していることをしかと実感した。
そして迎えた最終日、約六週間という期間お世話になった御献体への感謝の気持ちを胸に、納棺を行なった。御献体を棺に納めるときには、解剖実習の短い期間のみでなく、御献体の今まで歩んできた人生にも思いを馳せ、生前は会うことがなかった方との本実習での貴重なご縁を感じるとともに、命のつながりについて改めて深く考えた。
最後に、この解剖実習を通して多くのことを教えていただき、医学の道を歩み進めさせていただいた、ご献体いただいた故人、そしてそのご家族に心の底より御礼申し上げます。
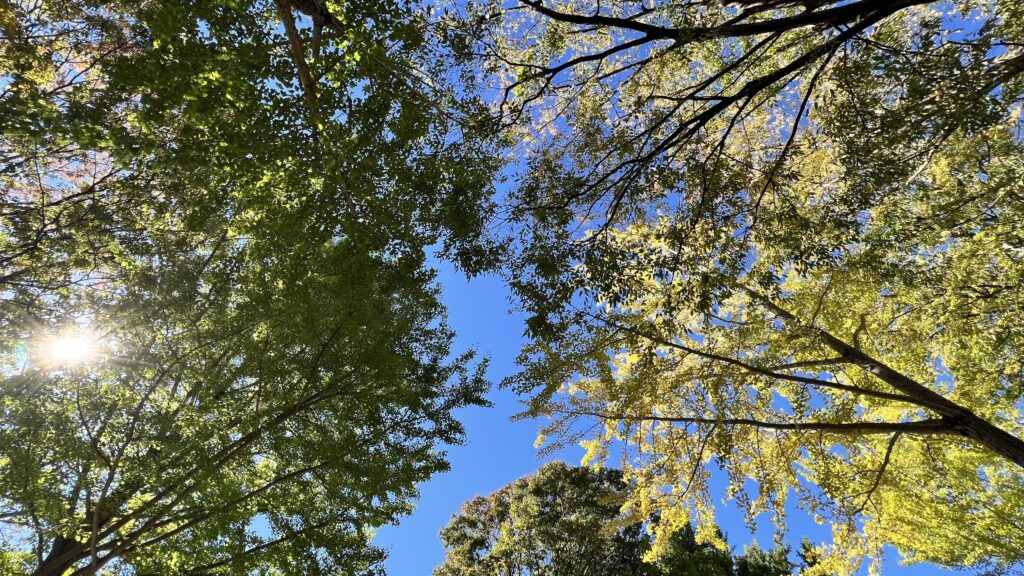
解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 砂川将太
納棺式の日、私はご遺体を棺に納めながら6週間にわたる実習を思い返していた。私はこの6週間で何を学ぶことができたのだろう。
解剖実習が始まる前に私が教科書や手引きを見て最初に感じたことは、こんなに膨大な量の血管や神経、筋肉等の身体の構造を覚えることができるだろうかということであった。このような不安から私は教科書や手引きで予習してから実習に臨んだ。しかし実際のご遺体で予習した構造を確認しようとしてもよく分からず、気づけばその部分を切ってしまっていたこともしばしばであった。教科書では同じ身体の部位でも血管のページには血管だけ、筋肉のページには筋肉だけ、神経のページには神経だけ、というように描かれていることも多く、なかなか身体の立体感を理解できずにいたことも原因の一つだろう。
解剖について勉強する上で、教科書で基本的な知識を学習することは重要だがそれだけでは全く不十分だった。解剖実習を通して教科書ではなく自分の目の前にいるご遺体こそが先生であり、ご遺体から学ぼうとすることこそが重要であると痛感した。目の前にいるご遺体は教科書の人体図とは異なる一人の人間である。その身体が実際にどのように成り立っているのかを考えながら剖出を進めることで各組織や臓器の構造や特徴、関連をより深く理解することができた。教科書だけではあまり理解することができずにいた身体の立体感も実際に自分で作業することで理解することができ、最初は膨大とも思えた知識が自然と覚えられた。
実習の後半では実習の日々にも慣れてきて毎日ご遺体から学ぶことに集中できるようになっていた。このころには呼吸や食べ物の消化などといった身体活動に関わる身体の器官とそれを栄養している血管の構造などといった身体の構造の緻密さに感嘆することの連続だった。
納棺式の日に生前の姿からは程遠いビニールに包まれたご遺体を棺に納めた時に、私は献体という選択をされた故人やご遺族の崇高な意思を感じた。そして医師の育成や医学の発展に寄与するために自分の身体や家族の身体を解剖されることを承諾してくださったという事実と、そのご遺体を私が解剖させていただいたという事実を改めて認識した。故人とその遺族の崇高な意思を自分が受け継いで一生をかけて学び続けなければならないことを実感し身震いすると同時に、医学の道を選んだ者としての使命を感じた。
今回の解剖実習は私にとって一生忘れないほど貴重な経験になった。最後に解剖実習の準備や指導をしてくださった先生方、そして何より献体という難しい決断をしてくださった故人とそのご遺族に心から感謝申し上げます。

解剖実習を終えて
2024年度 医学類2年 伊藤至秀
「ご献体頂いた故人とそのご遺族の尊い意思に感謝して黙祷」という号令が毎日かけられたが、私は解剖実習期間中に「尊い意思」について考えていた。亡くなった後に自分の体を医学教育のために使って良いという選択は確かに素晴らしい意思であり、私のような医学生が感謝しなければならないことも理解できる。しかし日常的に尊いと思わない私にとっては、「尊い」とは何なのか、何がどのように「尊い」のか、よく分かっていなかった。
解剖実習の初日、当たり前のように解剖台に安置されている37人のご献体に若干の恐怖を覚え、かなり緊張しながら作業が始まったが、特段の尊さを感じることはなかった。初日は目の前の状況を飲み込むことに精一杯で、気持ちの整理をする余裕が無かったように感じる。私は今までの人生で葬式にさえあまり行ったことが無く、亡くなった人間の体に触れることもなく、当然ながら生死問わず人体の内部を自分の手でかき分けたことも無い。初日は上半身を担当したが、一番最初に正中線にメスを入れる時に手が震えたことをはっきりと覚えている。初日終了時には、感情的に「疲れた」という気持ちが強く、「尊い」と思う間も無く実習が終わってしまったと思う。
最初の1週間が終わる頃には解剖にもかなり慣れてきて、気持ちにも余裕が生まれた。解剖中に目の前のご献体についてふと考えるようになり、よくお顔をまじまじと眺めていた。どのような人生を歩んでここまで来たのか、どんな家族構成で育ったのか、ご結婚されたのか、子供や孫はいたのか、どんな最期を迎えたのか、などと勝手に想像していた。もちろん答えは返って来なかったが、個人的には献体に同意した理由が気になった。日本全体でも世界全体でも、献体する人よりも献体しない人の方が圧倒的に多い。事実、私の周りにも献体した人はいない。つまり、献体された故人には、敢えて献体を希望した経緯があるはずであり、私は献体に同意した理由を知りたいと思った。
2週目の帰宅後に「筑波しらぎく」を読んで、私は答えを得たと感じた。「筑波しらぎく」は筑波大学白菊会の会報であるが、そこには解剖実習を終えた2年生の感想文と共に、献体された故人の生前の言葉が載せられていた。名前は載っていないので誰が書いた文章なのか分からないので、過去のご献体の誰かの言葉であるが、献体に同意した理由が書かれていた。曰く、自分は年をとって他人に世話と迷惑をかけるばかりであるが、こんな自分でも最期に人の役に立てるなら、是非自分の体を使って欲しい、と。恐らく何の関わりも無いであろう医学生のために役立って、亡くなっても社会に貢献しようという姿勢に感銘を受け、この姿勢にこそ「尊さ」が宿っていると感じた。
私は、亡くなっても社会に貢献しようという「尊い意思」をご献体に見せて頂いた。私も社会に貢献しようという「意志」を行動に表したい。

解剖実習を終えて
2023年度 M2
「みなさんの先生はご献体です」これは最初の授業で言われた言葉であった。聞いた時は実感こそなけれ、献体いただいた方への敬意を示せということなのだろうと受け止めていた。実際に解剖実習が始まると、限られた時間の中で、目の前の組織・筋肉・神経・血管などを覚えるのにただただ必死で、その意味について考える余裕はなくなっていた。
数週間して足の筋肉の解剖をしていた際に、同名の筋肉が左右で大きく異なることに気付いた。先生に聞いてみると、例えば杖をついていらっしゃったり、片側の足が不自由でいらっしゃったりするとこうして左右の筋の大きさが異なることがままあるとのことであった。脇目も振らず必死になって解剖してきたがその時に初めてご検体いただいた方の生前のお姿や生活に思いを馳せた。今、目の前の方は、どのように生まれ、どのような人生を送り、そしてご献体いただくという結論にいたったのか、またご遺族の方々はその決心をどのように受け止め、賛同してくださったのか、そういった思いが巡った。
ある種、恐ろしいことではあるが、初めのうちも決して怠惰な考えや適当にやればよい、などと考えていたわけではない。真剣に取り組んでいるからこそ、目の前のことに集中してしまっていた。そのあまり、その方の生活や人生を考えることを失念してしまうということは、将来、医師として多忙に、真剣に働く中でも陥りやすい状況なのではないかと推察する。しかし目の前の病理に集中するあまり、患者の生活や人生に思いを馳せられなければ、良い医療ができるとはいえないだろう。私はその時に初めて、「先生はご献体だ」ということの意味を実感できた。また、当然ではあるが、教科書通りでない三者三様の体の作りや、立体で見た時の見え方の違い、色や細かな形などはお一方お一方のお体をみることによって初めてわかることである。人体の構造の複雑さを、そして医療者として人の体や命に向き合うということを教えてくださった故人に深い感謝の意を表したい。
ご献体いただき、6週間あまりも毎日お体を見させていただいた方のお名前や生活について我々は全く知ることができない。少しでもご献体いただいた方について考えたいと思い、解剖実習を終えて、『白き旅立ち』という本を読んだ。そこには日本で初めて献体をしてくださった方の半生がフィクションも含め描かれていた。献体いただいた方の本当の思いはもちろん本からもわからない。ただ、死後に解剖されることの忌避感を超えて、医学の発展のために献体を希望される経緯はどんなものであれ、真摯に考えていきたい。
さらに、恥ずかしながら献体の歴史についても本実習を通じて初めて学んだ。白菊会の設立の経緯や『白き旅立ち』に描かれた医師らの解剖に対する熱意も、今の恵まれた状況との違いを強く実感した。我々は制度化された医学教育の中で、ご献体を準備され、清潔に、安全に整備された部屋で解剖を行うことができる。解剖実習を行えることをどこか当然のように感じてしまっていないだろうかと思う。解剖がこのように行えるように尽力した歴史上の方や、何よりもこれまで医療の発展のために献体いただいたすべての方にも改めて感謝申し上げたい。
最後ではあるが、夏季休暇を利用して慰霊塔と、篤志解剖第一号の献体をしてくださった美幾さんの墓を参った。これまで我々がこのように学ぶことができるように尽力いただいた方への感謝は、今後、医療者として真摯に学び、そして働くことで初めて還元できる。その思いを忘れずに今後も勉学に励みたいと思う。

6週間の解剖実習はあっという間だった
2023年度 M2
6週間の解剖実習はあっという間だった。毎日御献体と向き合い必死で彼女から学んだ6週間は、今までの大学生活で一番濃密で、生涯忘れないと確信できるものであった。
解剖実習についてはいろいろな先輩方から事前に話を聞いていたが、想像すらできていなかったのだと知ったのは解剖実習室に初めて入った時だった。御献体を包む真っ白な布も、ひんやりとした空気も、どこか自分が違う場所にきてしまった不安感を私にもたらした。そして、同時に、この場所での6週間を無駄にしないように全力を注ごうという覚悟も生まれた。
その覚悟を胸に毎日毎日予習復習に追われながら解剖をしていたが、満足いく日はほとんどなかった。最初の方は神経の位置を把握せずに実習にのぞんでしまい、たくさんの神経を傷つけた。その時感じたのは恐怖だった。一度傷つけてしまったら取り返しがつかないことを実際に経験し、もしもこれが手術であったら自分は患者の命を奪っていたのかもしれないと思うと恐ろしくなったのをおぼえている。勉強の仕方を学び次第に剖出できる様になっても、御献体に謝ることは多かった。休み時間を削っても、夜遅くまで残っても学びきれないほど多くのことを御献体は教えてくれ、座学で文字ばかり追ってきた私は驚いてばかりだった。全身に張り巡らされる神経や血管の位置、その繊細さは想像と全く違っていたし、逆に臓器の構造は学んだ通りであった。発生学とも組み合わさって、各臓器と神経のつながりは非常に興味深かった。解剖の先生の1人が、解剖に詳しいからこそ自信を持って治療を行うことができるとおっしゃっていたがその通りであると思う。人体の複雑な構造を理解することは容易ではないが確実に医療行為に直結する。医師になるにあたって解剖は絶対に必要なものなのだと切に感じた。
「御献体くださった故人とその遺族の尊い意志に感謝を」。これは毎日の解剖前後の黙祷の際の言葉だ。解剖で御献体と向き合う時、いつも“尊い”という言葉はぴったりだと思っていた。御献体がなければ私たちはこの様な学びの機会を得ることができなかった。きっと故人も御遺族の方々も、これからの医療の発展につながると信じてわたしたちに体を預けてくださったのだろう。故人の生きている時に会うことは叶わなかったが、亡くなってからも私たちへの期待は感じることができた。今回の解剖で私は本当に未熟であるということが浮き彫りになったと思う。しかし確実に医学生としての意識は大きく変わった。故人の方、御遺族の方の尊い意志を、期待を、無駄にすることのないようにさらに精進していきたい。
6週間に及ぶ実習を支えてくださった全ての方々への感謝は忘れません。本当にありがとうございました。

解剖実習を終えて
2023年度 M2
今日の最終試験をもって解剖実習が完全に終了しました。1か月半という密なスケジュールは長いようで短いものでした。
初めてご遺体と向き合ったときご遺体はとても安らかな顔をされていました。その顔を見ていると、「これからこの方の体をお借りして、たくさんのことを勉強させていただくのだ」と身の引き締まる思いがしました。初日の皮切りはご献体くださった方の組織を壊してしまいそうでほんとうにおそるおそるでした。
教科書やバーチャル上で予習してもわからなかったことが、いざ解剖実習を行って実際に自分の手で触れたり目で見たりして観察することで、自分の中で「そういうことだったんだ」という理解に変わる瞬間を何度も体験しました。その反面、正常とは異なるものを見たときの違和感や混乱も体験しました。実際にご献体に触れて見て感じたことが自分の知識として蓄えられていくのをひしひしと感じました。教科書上の学習のみならず、実際にご献体を解剖することで得られるものはこれからの私にとってとても大きな糧になったと思います。このような機会を与えてくださった、ご献体くださった方やそのご家族の方には感謝してもしきれないです。
私たちの班のご献体は90歳で亡くなられた方でした。その方の死因は誤嚥性肺炎でしたが、心臓に大動脈瘤があったり、大腿上部に壊死が見られたりと、死因との直接的な関連はなさそうな「異常」が多くみられました。そのような部分は決して「健康」とは言えないものかもしれませんが、ご献体くださった方がその人自身の人生を生き切ったのだろうということを強く感じさせ、心にぐっとくるものがありました。
今回の解剖実習を通して、人体の基本的な構造を知ること、そして一人一人の体の構造は皆少しずつ異なることを理解しておくことがこれからの学習や臨床、研究の場でいかに重要であるかを学びました。例えば、手術において基本的な血管や神経の走行や筋肉や臓器の配置を理解することはもちろん重要ですが、その走行や配置が患者さん一人ずつ少しずつ異なると知っておくことは、誤って組織を傷つけないために非常に重要だと改めて感じました。
今回の解剖実習では本当に多くの学びがありましたが、この期間だけで何もかも理解することはもちろんできませんでした。だからこそ、これから自分のわからなかったことを突きつめ、自分の理解に変え、さらなる学びに昇華させていきたいです。これが医療の発展のためにご献体くださった方やそのご家族の気持ちに応えることにつながると信じています。
ご献体くださった方とそのご遺族の方、このような大事な機会をくださり本当にありがとうございました。

解剖実習を終えて
2023年度 M2
自分自身の身体について理解したい。これは私が医師になりたいと思った理由の一つだ。私はずっと、生まれた時から使っているこの身体を、ある程度、意識的にコントロールできていると思っていた。実際には、身体の中で自分の意識通りに動かせている部分はたった一部であって、医学的な知識のある人ならそれは当たり前のことのように感じるかもしれない。しかし私は、病気になって初めて、自分の身体は必ずしも自分の思い通りにできるわけではないのだという実感を持った。そこで、如何に自分自身の身体について知らないのか痛感させられ、それについて学びたいという目標を持った。振り返ると、この解剖実習を通して漸く、その目標を達成するためのスタートラインに立てたのではないかと思う。
今まで私は、身体の全体的なイメージが掴めていなかったため、医学について学んでも、その内容と自分自身の身体と結びつけて考えることができていなかった。しかし、解剖実習を進めるにつれて、私達の先生である目の前のご献体を通して学んでいる知識を、自分の身体に投影することができるようになった。
解剖実習で人間の身体に実際に触れて、その中を剖出していく過程は衝撃的だった。今まで座学で人間の身体について勉強してきたのとは違う、リアルな学びだった。また身体をバラバラにして学ぶのではなく、一体のご献体で、すべてが繋がった状態を見ることができた。そうすることで、身体を形作る構造のうち、一般的な部分と特殊な部分とを分けて認識することができるようになったと思う。
また、解剖実習を通して、医学を学ぶ姿勢に変化が生まれた。解剖実習開始直後は、分からないことが多く、手引きを読んで与えられた課題を必死にこなすことで精一杯であった。しかしながら、中間諮問の前後で、自分たちだけで解剖に取り組むと、どの部分が重要なのか分かっていないことに気づいた。先生方に質問をすると、いつでも広い視点から、全体の理解に役立つ回答をしてくださった。独りよがりになるのではなく、より広い知識を持つ人を頼って学習をすることの重要性に改めて気付かされた。
最終諮問では、先生が発生学と絡めて心臓の解説をしてくださった。私がその中で衝撃を受けたのは、心繊維三角についての解説だった。初めてその言葉を知ったとき、繊維という言葉が脈絡もなく登場したことに軽く疑問を抱いていた。しかしながら、それについて深く調べることはないまま、諮問の日を迎えた。当日、洞房結節から発生した電気信号が、房室結節へ伝わった後、心室全体へ伝わってしまわないのはなぜか、それを可能にする構造は何か答えよという質問があった。その答えこそが心繊維三角であり、つまりそれが絶縁体の役割をする構造であると分かった時、繊維という言葉とその役割が結びついて、感動を覚えた。今までの自分の疑問が解消されただけでなく、こういった印象的なエピソードを結びつけて覚えることで、丸暗記から脱し、理解の上で記憶に留めることができるのだと気付いた。これから学ぶ医学のどのような内容でも、自分よりより広い視野や知識を持つ人から積極的に話を聞くことが、深い知識の定着への近道になると学んだ。
この六週間は、非常に苦しかったが自分の成長を実感できる時間となった。最後になりますが、ご献体頂いた故人と、そのご家族の方々、本当にありがとうございました。私たちの成長、医学の発展を願い、このような貴重な機会をくださったこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回学んだ知識だけでなく、感じた思い、この解剖期間に私たちの学習を支えてくださった皆様の存在を忘れることなく、多くの人を救える医師を目指して勉学に励んでいきたいと思います。

解剖実習を終えて
2023年度 M2
解剖実習の初日、実習室に入った時の静かで重苦しい空気、そこから受けた緊張を忘れることはないだろう。実習を行った6週間は、1つでも多くのことを理解して覚えようとしてひたすら勉強を続ける日々であると同時に、本当に貴重な経験をさせていただいた期間であった。
解剖実習を振り返ると、最初のうちは解剖を学ぶことの難しさを実感して苦悩していた。解剖した構造の区別がつかず、覚えるべき解剖学名の多さに対応できずにいて、実習書とご献体を丁寧に照らし合わせなければその構造の名前が分からなかった。しかし先生方に質問すると、筋肉や骨、血管、神経の名前をご献体の前ですぐに示して教えてくださった。なぜそのようなことができるのか分からず、悩んでいるところで先生方に相談すると、その構造が人体において果たす役割や他の構造との関係を考えるよう助言をいただいた。例えば筋肉であれば、その筋肉がどのような運動をする際に役立ち、どの血管が栄養してどの神経が支配しているか、といった具合である。そのことを考えて初めて、人体の1つ1つの構造は単独で存在するのではなく協調して機能していることと、他の構造との関わりや位置関係から定義されることが理解できた。そして、解剖した構造の名前が自然と頭に入り、人体をより深く理解したいという強い興味を持って実習に取り組むことができるようになった。また、ご献体と本当の意味で向き合って解剖を行えたのはこの頃からだと思う。実習書と比較して解剖した構造を確認するに留まらず、解剖して目の前にある構造の全てとそれが果たす役割や他の構造との関係を理解する。そのために、自身の体をもって解剖学を教えてくださるご献体と真摯に向き合い、実習の中で没頭して考えることができるようになっていった。
解剖実習の最終日、納棺の際に抱いたのは大きな感謝の気持ちであった。実習を通して、人体の構造の複雑さや精緻さが十分に実感できた。解剖した構造は、そのどれもが生きていくために何らかの役割を果たす重要なものだろう。その1つ1つを自分の目で見て理解し、それらが協調して人体を動かす不思議さに大いに感動した。そのような機会は今後二度と得ることのできない、貴重なものだろう。そして医学を学ぶ際に、将来は医師として働く際に、実習で学んだことを活かしたい。実習の中で向き合い続け、多くのことを教えてくださったご献体に感謝と敬意をもって手を合わせ、納棺を終えた。
最後に、ご献体くださった方とそのご遺族の方々、解剖実習に関わってくださった先生方、協力して解剖実習を行った仲間に感謝を込めて。誠にありがとうございました。

解剖実習を終えて
2022年度 M2
解剖実習を行うまでの大学生活は、医学の中でも高校生物と重複するような基礎的な内容について講義を受けたり実験をしたりすることが多かったので、自分は何の変哲もない理系大学生であるという認識であった。しかし、解剖実習を通して、自分が将来医師になるために素晴らしい環境で勉強させていただいている医学生の身分であるということが強く感じられた。解剖実習は、医学生が教育者の監督の下でのみ行うことが法的に許可されていて、看護学生や薬学生はご遺体を観察することはあっても触って確認することはできない。手順にのっとってご遺体を開いていき、自分の見たいものを探求するという行為は、医学生の特権といえるのだ。
そのような貴重な体験から私が学んだことは、本来見ることの許されない面を見えるようにすることへの感動である。医師になる上で、人体の構造をマクロな視点で理解しておくことは非常に重要であるが、頭に入れておくべき構造のほとんどが皮膚より内側に隠されている。四肢に関して言えば、普段から皮膚の外から見えている血管や筋肉はほんの表面の一部にすぎず、より深部には太い動脈が走っていたり、神経が支配する筋肉を貫いていたりするということは、皮膚や結合組織を切って取り除いていかなければ絶対にわからない。臓器に関して言えば、肺のスポンジのような質感や、腸が腹膜の内側に美しく収まっている様子は、解剖実習を通して初めて理解することができたことである。特に私が驚いたことは、頭頚部での脳神経の走行がとても整頓されていたことである。たくさんの枝分かれをしてそれぞれの標的の筋や器官に分布をしている姿はまさに教科書に書いているものと同じであり、こうしてヒトの構造が正しく成り立っているから、我々は見たり、聞いたり、笑ったりするという動作をすることができるのだと感動した。 最後に、この解剖実習を通して、学んだことがもう一つある。それは、解剖実習をするにあたって必要な体力や覚悟は、医師となって患者を救っていくことへの準備に大きくつながっているということである。正直に言うと、6週間でかなりの体力を消耗し、手順通りに進まないことでストレスが溜まって精神がすり減ることも多かったので、想像していた以上に大変な実習であった。しかしこの実習によって得られた心構えや体力によって、医師になってからの長時間の勤務や大きな仕事にも耐え抜くことができるのではないかと思う。

解剖実習を終えて
2022年度 M2
2022年5月16日、解剖実習の初日。初めて入った解剖実習室の中は独特の緊張感が張り付めていて、少し肌寒さを感じた。実習のガイダンスを聞いたのち、巻かれていた布を丁寧に外して、初めてご献体と対面した。肌の色は血の気がなく薄く、少しホルマリンの刺激臭がした。肌に触れてみると、硬くひんやりと冷たかった。一見ただ寝ているようにも見えるご献体からは、近くで見れば見るほどに「死」を感じられた。
初めてメスを握り、ご献体の体に傷を入れるとき、私は何度もメスを入れるのをためらった。メスを使う恐怖心や作業が正しいのかの不安などもあったが、ためらってしまった一番の要因は、医師に向けて大きな一歩を踏み出す勇気がなかなか振り絞れなかったからだと思う。これをすれば自分が大きく変わってしまう、もう後戻りはできない人生の分岐点であるかのようにあの時感じられた。
実習が進むにつれ、ご献体の筋肉や血管、臓器などの様々な組織を観察し、日々多くのことを学ばせていただいた。百聞は一見に如かずとよく言うが、教科書やイラストで学ぶよりも実際に自分で剖出して観察する方がより鮮明に記憶することができた。約2か月という短い期間ではあったが、これまでのどんな授業よりも濃密で充実した時間を過ごすことができた。初めは怖がってゆっくりとしかできなかった剖出の操作も日に日に上達していき、だんだんと丁寧かつスムーズにできるようになっていった。
解剖実習を通して私は、人という生命の奥深さや神秘さを身に染みて感じることができた。ヒトの体の中には心臓があり、肺があり、筋肉や骨があることは当然のように知っていた。しかし、いざそれらを自らの手で剖出して初めて肉眼で見たとき、「あ、ほんとにこれらの臓器たちが私たちの体の中で働いているんだ」と実感することができた。いままで文字やイラストでしか知らなかった医学の知識たちが、急に現実味を帯びてきたように感じた。これから医師として相手していく人の体というのは、これほど複雑でこんなにも美しいのだと気づかされた。また、実習中に他の班のご献体を見させてもらったとき、同じ体の部位でも大きさや色、形が人それぞれ全く違って見えることに驚いた。中には、がんで肺が肥大している方や大きな動脈瘤がある方もいた。一人一人のご献体をよく見ると、その人が経験した痛みや辛さ、生きるために手術をした跡、懸命に生きてきた証を感じ取ることができた。医師として人を診るということは、その人の人生を診ることなのだとわかった気がした。
この2か月間の実習で学んだ知識、感じたこと、すべての貴重な経験を忘れることなく、これからも医学の勉強に励んでいきたいと思う。
最後に、実習の指導や準備をしてくださった先生方、そしてご献体くださった故人とそのご遺族に深く感謝申し上げます。

![]()